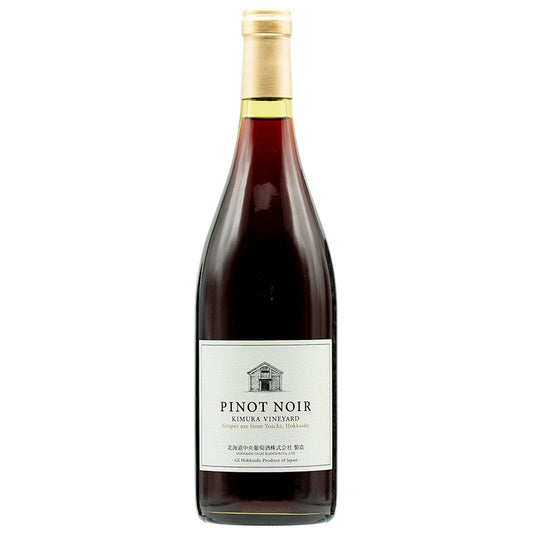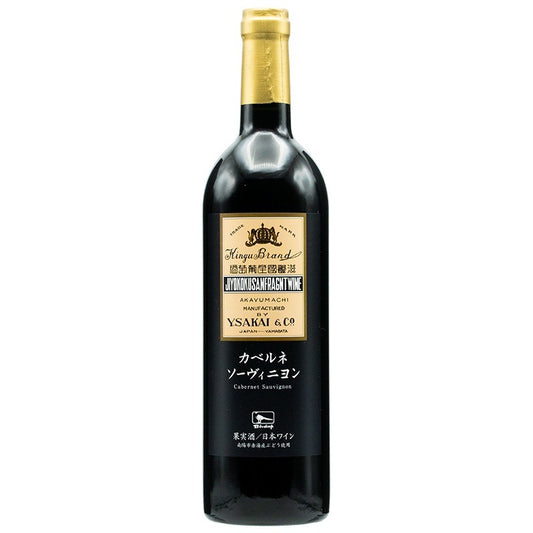出羽三山の一つ「月山」。
その麓に広がる水隗「月山ダム」に始まる水流は、山肌を削りながら蛇行し、庄内平野を横切って日本海へ注ぎ込む。その山間部、埜字川が削り落とした谷間の河岸段丘上に「庄内たがわ農業協同組合・月山ワイン山ぶどう研究所」のワイナリーは位置している。
 ▲日本海側に連なる山々からは、冷たい風が吹き下ろす
▲日本海側に連なる山々からは、冷たい風が吹き下ろす
背後には、山頂付近を既に雪に覆われた月山連峰、すぐ脇には深い谷を走る急流と、険しい自然に囲まれたその土地には、田畑を敷くに充分な平地がなかった。 「中山間部というお米も取れない土地で、雪も高く積もりますから、冬季の仕事がないのです。そういった中、北海道の池田町をモデルにした事業として、山から採ってきた「ヤマブドウ」を使ったワイン醸造がスタートしました。」
 ▲ 垣根に仕立てられた、月山ワインのもう一つの旗印「山ソーヴィニヨン」は、積雪に備え幹を強く傾けられている。
▲ 垣根に仕立てられた、月山ワインのもう一つの旗印「山ソーヴィニヨン」は、積雪に備え幹を強く傾けられている。
知識もノウハウもないところからスタートした月山のワイン造り。50年の歳月を経た現在では、 人工受粉やクローン選定の技術が飛躍的に向上し、日本古来の品種としてのヤマブドウの魅力を表現できるクオリティを得られるようになった。今では130軒にも上る栽培農家が、その栽培に取り組んでいる。
今では、ジャパン・ワイン・チャレンジ等の規模の大きなコンクールでの受賞歴も輝かしく、山形を代表するワインとなりつつある「月山ワイン ソレイユ・ルバン 甲州シュール・リー」であるが、当時は庄内の甲州に対する認知はほとんどなかったそうだ。
 ▲ 最早樹齢の分からない甲州の老木には、コケ類が繁茂するだけでなく、雑草すらも根を張っている。
▲ 最早樹齢の分からない甲州の老木には、コケ類が繁茂するだけでなく、雑草すらも根を張っている。
「庄内の甲州は非常に品質が高くて、中には糖度が20度を超える収穫もあります。 今年の10トン収穫でも平均で18度を超える糖度の葡萄を得ることができました。また補酸をしなくてもいいくらい酸もしっかり残ります。」
「また、平成15年からボルドー液の散布をしていないので、甲州独特のパッションフルーツのような香りが、年によっては明瞭でないこともありますが、年々濃く現れるようになっています。」 その品質は一朝一夕で得られたものではない。 「甲州と言えば山梨県」というステレオタイプから、他の産地をどうしても新興産地のように見做してしまうところがあるが、庄内の甲州葡萄栽培の歴史、その始まりは江戸時代まで遡る。
 ▲ 甲州栽培の北限に佇む葡萄畑。
▲ 甲州栽培の北限に佇む葡萄畑。
「江戸時代中期、酒井藩氏が甲州ブドウを藩内へ持ち帰り、城内に植えたことが、この土地の甲州ブドウのルーツです。葡萄の房が垂れ下がるのを見て、「武道が下がる」と城内から取り除かれてしまうのですが、それがきっかけで藩内に広く伝搬しました。」
葡萄畑から程近くに位置する河内神社。その境内の片すみに大正15年に建立された「葡萄圃復興記念碑」と記された石碑が、木陰の中でたたずんでいる。
 ▲「葡萄圃復興記念碑」
▲「葡萄圃復興記念碑」
 ▲ 歴史を感じる、レトロなフォントと配色の看板が月山ワインの目印。
▲ 歴史を感じる、レトロなフォントと配色の看板が月山ワインの目印。
現在、月山ワインを代表するのは、ヤマブドウ、山ソーヴィニヨン、甲州、セイベルの4品種。農協による経営という条件の中で、新しい品種の栽培を始めるのは簡単なことではないが、阿部さんの意思の下、欧州品種の栽培・醸造に取り組みを開始している。
「(農協の)組合員と一緒にワイン作りをしているので、思うような品種が中々作れないというジレンマもありますが、その一方で、5-6年前から農家さんのお願いして、欧州系の品種を少しずつ増やしてもいます。白葡萄としては、ピノ・グリやシャルドネ、ゲヴュルツ・トラミネール、ソーヴィニヨン・ブランを。黒葡萄には、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、メルロ、ピノ・ノワールの栽培を開始しました。 まだクオリティの面では課題がありますが、既に収穫も得られています。」
中でも、既にシャルドネやカベルネはリリースされている。特にカベルネは、山形県で優れた実績を残している品種であることも手伝ってか、バランスに優れた飲み口のいい逸品に仕上がっている。
2003年に入社した阿部さんは、2005年の鶴岡市による(旧)朝日村(月山ワイン所在地)の吸収合併に伴い、消えていく村の名前を冠した「ソレイユ・ルバン(仏語:朝日が昇る)」をリリースした。彼が抱く土地を大切にしようという誠実な思い。それがこの先、ワイン産地としての庄内を明るく照らしてくれることを期待する。