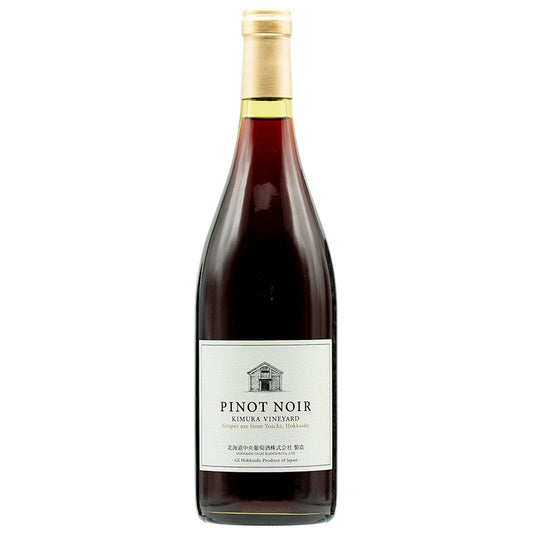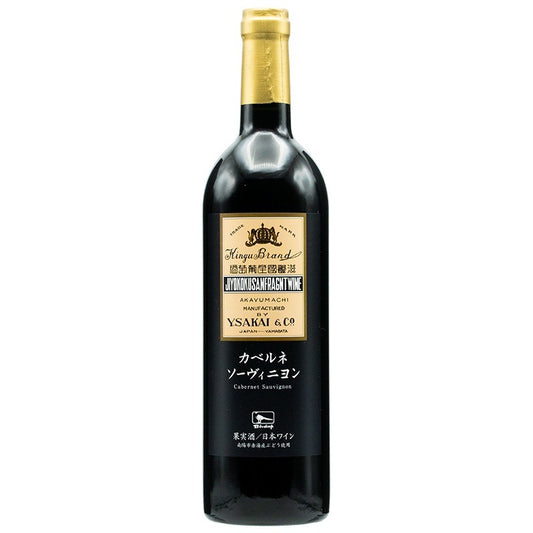北澤ぶどう園は現在で3代目となるブドウ栽培農家です。初めは生食用のブドウを中心としていましたが、3代目の文康(のりやす)さんの代からはワイン専用品種の栽培もスタート。
現在は委託醸造のみですが、ゆくゆくは自身のワイナリー設立しワイン造りまで手掛けることを目標としています。
 ▲ 「人の下で働くのは好きでないから自営が合っている」と笑う北澤さん。
▲ 「人の下で働くのは好きでないから自営が合っている」と笑う北澤さん。北澤ぶどう園は千曲市内に位置し、長野市の善光寺と松本市を結ぶ善光寺西街道の桑原宿にある。元々は桑栽培が盛んで、その後リンゴ栽培が主流になった地域だ。そんなリンゴ全盛期の時代に、巨峰栽培を始めたのが初代。そして、2代目は周囲が巨峰ばかり育てていた30数年前に、ワイン用ブドウの栽培を始めた。
北澤家はブドウ栽培のサラブレッドであり、開拓精神に溢れたファミリーなのだ。好奇心旺盛かつ高い技術力を受け継ぐファミリーだからだろうか、現在育てている生食用ブドウの品種は30種類以上!そんな北澤さんが3代目を引き継いだのは2013年。先代の不慮の事故によるものだった。就農してから10年程経っていたとは言え、不安もあったのではないかと思うが、北澤家の開拓精神を受け継ぎ、ある挑戦に取り組んでいる。
ワイン造りだ。
 ▲ 北澤ぶどう園の段々畑になっているブドウ畑の様子。
▲ 北澤ぶどう園の段々畑になっているブドウ畑の様子。ワイン造りに興味を持つと共に、改めて赤ワイン用の黒ブドウ品種を栽培したいと考えたそうだ。
自分の好きな品種を栽培したいという気持ちはもちろんあるが、品種を選ぶ際に重視したのは、「ブドウの出来の良さ」と「差別化しやすさ」の2点だ。自分が育てる上でも大事ではあるが、この点がクリアできれば、周辺の農家が新たにワイン用ブドウ栽培を始める際のハードルがぐっと低くなると考えた。
そして、この条件を元に20品種程試験栽培を行い選んだのが…マルベックだ。
マルベック?聞いたことがない…という方もおられるだろう。ピノ・ノワールやカベルネ・ソーヴィニヨンといった超有名品種に比べると知名度が下がるのは否めないが、侮ってはいけない魅力的な品種だ。フランス南西部カオールが原産と言われる黒ブドウで、「黒ワイン」と呼ばれるほど色調が濃いのが特徴。20世紀半ばまではボルドーでも人気を博したが、冷害で栽培量がガクンと減ることに。
一方、フランスからアルゼンチンに持ち込まれたマルベックは、1980年代頃から栽培が拡大し、現在では世界の栽培量の殆どを占める一大産地となり、名声を集めている。マルベック=アルゼンチンと認識されている方も多いのではないだろうか。ブラックベリーやブルーベリーといった黒系果実やスミレのようなお花、コショウのようなスパイス香があり、豊富なタンニン、酸味、果実味とのバランスが◎。そしてフルボディなのに口当たりは滑らか、フルーティーでジューシーな味わいなのも特徴的。癖になる味わいなのだ。
マルベックを推すにはワケがある
日本全国でワインが造られるようになった今でも、マルベック単体で仕込まれるワインは殆どない。そんな中、北澤さんが、半ば偏愛的に(失礼!笑)マルベックを推すのには理由がある。
高品質なものが育つ
まず驚いたのが、品質の高さ。試験栽培したマルベックの糖度は非常に高く、酸持ちもよい。色調も濃く仕上がり、タンニンとアルコール感も感じるしっかりとしたフルボディタイプのワインになった。フランス産やアルゼンチン産とは違う味わいではあるが、一口飲めば、マルベックだと分かる。品種特性と産地特性がしっかりと表現され、納得の仕上がりになった。2017年から収穫しているそうだが、どのヴィンテージも品質が安定しているそうだ。
実は、マルベックの片親はメルロの片親でもあり、マルベックとメルロは片親違いの兄弟。「長野県が日本を代表するメルロの産地であることを考えると、マルベックも長野に合う素質はあるはず」と北澤さんは分析する。
 ▲ マルベックは垣根仕立て(ギヨ・ドゥーブル)で育てられている。ブドウ木の下に咲く黄色いタンポポが春の訪れを感じさせる。
▲ マルベックは垣根仕立て(ギヨ・ドゥーブル)で育てられている。ブドウ木の下に咲く黄色いタンポポが春の訪れを感じさせる。栽培がしやすく収量が取れる
品質が高いと同時に、栽培しやすいというのは農家としてありがたい側面だ。マルベックが完熟するためには、豊富な日照量と適切な気温が必要と言われている。千曲市は長野県の中では温暖で日照量も多く、マルベックの栽培に適した土地だ。
北澤ぶどう園の圃場は東以外の3方を山で囲まれていることから、日の出も日の入りも早い。また、西側に山があることで夜間の気温も下がりやすく、酸落ちしにくい環境だ。それでも、メルロやシャルドネは少し酸落ちが気になるそう。そんな中、マルベックは世界的に見ても温暖な地域で栽培されることが多い品種なだけあり酸持ちがよい。それに、大きな病気も発生せず、育てやすい。更に、房付きもよく、収量制限も殆どする必要がなかった。


マルベック以外にもローヌ系品種であるシラーの出来も良かったそうだが、マルベックに比べると病気が出やすかったという。また、栽培人口も増えつつあり、差別化も難しい。ご自身はシラーを栽培しているが、他の農家に薦める上ではマルベックに軍配が上がる。
生食用ブドウの収穫とバッティングしない
いくらワインが好きとは言え、北澤さんの本業は30品種以上育てる生食用ブドウの販売で、収入の殆どを占める。そのため、生食用ブドウの収穫期とワイン用ブドウの収穫期が重なるのは避けたい。
マルベックの収穫時期は10月中旬以降で、生食用ブドウの収穫が終わった後だ。一方、シャルドネとメルロは生食用ブドウの収穫期と重なってしまうので、この点からも両立は難しい品種と判断したそう。因みに、カベルネ・ソーヴィニヨンやカベルネ・フランの収穫は生食用ブドウの収穫の後ではあるが、栽培人口も多く差別化が難しいので、ブドウ農家に推薦しにくいとのこと。
 ▲ 北澤ぶどう園のHPより。色も形も様々でつやつやの生食ブドウ達。見ているだけで涎が出てくる…
▲ 北澤ぶどう園のHPより。色も形も様々でつやつやの生食ブドウ達。見ているだけで涎が出てくる…特別な技術がなくても高品質な果実を安定的且つ高い収量で収穫できる。しかも生食用ブドウと忙しい収穫の時期が重ならない。「収量制限していいものを作る」というのがワイン用ブドウ栽培の鉄則のように語られることが多いが、北澤さんは違う。「収量制限せず、付いた実を余さず収穫しても品質が高いもの」を目指すのだ。なぜなら、ワイン醸造まで行う農家であれば、ブドウに付加価値を付けて販売することができるが、ブドウ栽培農家の場合、収量が上がらないと収益を得られないから。ブドウ栽培農家も潤うワイン用ブドウ栽培。これを目指すのが北澤さんなのだ。