日本ワインコラム
THE CELLAR ワイン特集
山梨・ダイヤモンド酒造
日本ワインコラム | 山梨 ダイヤモンド酒造 住宅地に佇むごく一般的な建築物。 一瞥してワイナリーらしい雰囲気はなく、むしろ、街の内科クリニックのような風体。多くの注意を惹きつけるような勇んだ姿勢を感じない看板くらいが、ここがワイナリーであることを教えてくれる。ダイヤモンド酒造。日本でも指折りのマスカット・ベーリーAの赤ワインを送り出す、山梨県随一のワイナリー。その地位に登り詰めた雨宮吉男さんは、マスクをしていること以外にほとんど外交的な要素を纏わぬ、ノーガードなスタイルで現れた。農作業の途中の人ならまだしも。 そして思った。多分その辺はどうでもいいのだ。 ▲ 筆者自身も桜をバックにおじさん2人のツーショットを取ったのは初めてだったが、撮られたほうも初めてだったのではなかろうか。ともあれ、中々趣のあるショット。 「勝沼は他の町に比べると、夜温が下がりやすいんです。「笹子おろし」と言って、笹子峠から夕方風が吹き下ろしてくるんです。だから、隣町の人は「勝沼って、夕方涼しいね。」って言うんです。でも、最近は気候が変わってきていて、あまり風が吹かなくなりました。 土壌は砂っぽくて、影響している山や川砂の影響が強いので水捌けがいい。 ▲ 契約農家の葡萄畑。「なんもないでしょ。」と言われたらそうなのですが、勝沼の砂っぽい土壌を識別いただけるだろうか。 最近はマグヴィスワイナリーさんが土壌分析をしていますが、今まではそう言ったことはやってなくて、何となくそういうものだろうという形でした。 なので、彼らの分析によって変わってくるところもあるのだろうと思います。 対して、(ダイヤモンド酒造の原料の)マスカット・ベーリーAが植えられている穂坂は、完全に粘土質です。なので、赤ワイン用品種に適している。「勝沼は甲府盆地の東の縁なので、朝日が遅くて夕日が長い。穂坂は盆地の西の縁。日の当たり方が真逆なんです。朝日が早くて夕日が短い。」 山梨県甲州市勝沼、果樹栽培のみならず、国内産ワインの発祥の地として知られる土地で、ダイヤモンド酒造はワイン造りを行なっている。 元々は、近隣の農家がそれぞれの葡萄を持ち寄ってワインをつくる自家醸造施設であったが、生産量が増えたことによって金銭のやりとりが発生すようになると、税務署指導もあって、雨宮家が酒造の権利を農家から買い取り、有限会社化。のちに株式会社化を果たし、現在にいたる。現当主の雨宮吉男さんは、勝沼や穂坂の契約農家からの葡萄を使って、ワイン造りを行なっている。 契約栽培先を選ぶなんてのは中々できないですよね。何かしらの人としての関係性もありますから。甲州に関しては一律の値段で買っていますが、ベーリーAに関しては、畑でできたワインのクオリティで葡萄の値段を決めているので、農協の30-100%増しくらいの値段になるんですが、そういった価格での差別化はしていますけどね。 買い葡萄のみを使用する、無理やりフランス風に言えば、ネゴシアン的なスタイルのダイヤモンド酒造。自身の理想のスタイルに近づくため、マスカット・ベーリーAの究極を目指すため、多くの注文をつけるのではなかろうか、とも思ったが、実のところはそうではない。 兼業農家や家族経営が多い中、雨宮さんが一人で各契約栽培先をコントロールすることは不可能であるし、産業としての構造がやはり山梨県とブルゴーニュでは、大きく異なる。この後引用されるデュジャックはそのネゴシアンブランドで契約農家の畑に強く介入することで有名だが、それに関するシンプルな疑問はやや筋違いということで解消しておく。そんなことが頭をよぎったのは筆者だけかもしれないが。 ▲ リーファーコンテナは古いので、冷却用にエアコンの室外機が繋がれている。 「農家さん達もどうしたらいいか、とか助言を求めることはあるので、こういう風にしたほうがいいんじゃないですか、というアドバイスをすることはあります。粘土質だと栄養素が抜けないので、肥料に関しても、最初からたくさん撒くよりも、足りなくなったら葉面散布で足せばいいということや、大きな房に価値がある生食と、コンパクトで凝縮した葡萄に価値がある醸造では考え方が大きく異なるので、摘房などに関して、こうしたらいい、ああしたらいい、は言います。 昔、ブルゴーニュのデュジャックに行った時に思ったのですが、デュジャックってモレサンド二の生産者ですが、ヴォーヌロマネの畑持ってるじゃないですか。でも、飲み比べてみるとモレサンドニの方が美味しいんですよ。それはやっぱり、元々モレサンドニの生産者だからかな、と思っていて。勝沼の人間が穂坂の人間にあんまりいうのは良くない。その人たちの方が土地をわかっているということだから、と考えています。」 ▲ 「リーファーコンテナを使って」とおっしゃっていたので、同機能の何かかと思ったが、本当にリーファーコンテナだ。 必ずしも意図的でないにしても、栽培に関しての自身の介入が少ない。雨宮さんが造るワインに対する評価は、醸造に多くのリソースを注ぐ、まさに醸造家としての彼の実力に与えられたものだろう。しかし、 (マスカット・ベーリーAに関しては) ちんたらやることですね。...
山梨・ダイヤモンド酒造
日本ワインコラム | 山梨 ダイヤモンド酒造 住宅地に佇むごく一般的な建築物。 一瞥してワイナリーらしい雰囲気はなく、むしろ、街の内科クリニックのような風体。多くの注意を惹きつけるような勇んだ姿勢を感じない看板くらいが、ここがワイナリーであることを教えてくれる。ダイヤモンド酒造。日本でも指折りのマスカット・ベーリーAの赤ワインを送り出す、山梨県随一のワイナリー。その地位に登り詰めた雨宮吉男さんは、マスクをしていること以外にほとんど外交的な要素を纏わぬ、ノーガードなスタイルで現れた。農作業の途中の人ならまだしも。 そして思った。多分その辺はどうでもいいのだ。 ▲ 筆者自身も桜をバックにおじさん2人のツーショットを取ったのは初めてだったが、撮られたほうも初めてだったのではなかろうか。ともあれ、中々趣のあるショット。 「勝沼は他の町に比べると、夜温が下がりやすいんです。「笹子おろし」と言って、笹子峠から夕方風が吹き下ろしてくるんです。だから、隣町の人は「勝沼って、夕方涼しいね。」って言うんです。でも、最近は気候が変わってきていて、あまり風が吹かなくなりました。 土壌は砂っぽくて、影響している山や川砂の影響が強いので水捌けがいい。 ▲ 契約農家の葡萄畑。「なんもないでしょ。」と言われたらそうなのですが、勝沼の砂っぽい土壌を識別いただけるだろうか。 最近はマグヴィスワイナリーさんが土壌分析をしていますが、今まではそう言ったことはやってなくて、何となくそういうものだろうという形でした。 なので、彼らの分析によって変わってくるところもあるのだろうと思います。 対して、(ダイヤモンド酒造の原料の)マスカット・ベーリーAが植えられている穂坂は、完全に粘土質です。なので、赤ワイン用品種に適している。「勝沼は甲府盆地の東の縁なので、朝日が遅くて夕日が長い。穂坂は盆地の西の縁。日の当たり方が真逆なんです。朝日が早くて夕日が短い。」 山梨県甲州市勝沼、果樹栽培のみならず、国内産ワインの発祥の地として知られる土地で、ダイヤモンド酒造はワイン造りを行なっている。 元々は、近隣の農家がそれぞれの葡萄を持ち寄ってワインをつくる自家醸造施設であったが、生産量が増えたことによって金銭のやりとりが発生すようになると、税務署指導もあって、雨宮家が酒造の権利を農家から買い取り、有限会社化。のちに株式会社化を果たし、現在にいたる。現当主の雨宮吉男さんは、勝沼や穂坂の契約農家からの葡萄を使って、ワイン造りを行なっている。 契約栽培先を選ぶなんてのは中々できないですよね。何かしらの人としての関係性もありますから。甲州に関しては一律の値段で買っていますが、ベーリーAに関しては、畑でできたワインのクオリティで葡萄の値段を決めているので、農協の30-100%増しくらいの値段になるんですが、そういった価格での差別化はしていますけどね。 買い葡萄のみを使用する、無理やりフランス風に言えば、ネゴシアン的なスタイルのダイヤモンド酒造。自身の理想のスタイルに近づくため、マスカット・ベーリーAの究極を目指すため、多くの注文をつけるのではなかろうか、とも思ったが、実のところはそうではない。 兼業農家や家族経営が多い中、雨宮さんが一人で各契約栽培先をコントロールすることは不可能であるし、産業としての構造がやはり山梨県とブルゴーニュでは、大きく異なる。この後引用されるデュジャックはそのネゴシアンブランドで契約農家の畑に強く介入することで有名だが、それに関するシンプルな疑問はやや筋違いということで解消しておく。そんなことが頭をよぎったのは筆者だけかもしれないが。 ▲ リーファーコンテナは古いので、冷却用にエアコンの室外機が繋がれている。 「農家さん達もどうしたらいいか、とか助言を求めることはあるので、こういう風にしたほうがいいんじゃないですか、というアドバイスをすることはあります。粘土質だと栄養素が抜けないので、肥料に関しても、最初からたくさん撒くよりも、足りなくなったら葉面散布で足せばいいということや、大きな房に価値がある生食と、コンパクトで凝縮した葡萄に価値がある醸造では考え方が大きく異なるので、摘房などに関して、こうしたらいい、ああしたらいい、は言います。 昔、ブルゴーニュのデュジャックに行った時に思ったのですが、デュジャックってモレサンド二の生産者ですが、ヴォーヌロマネの畑持ってるじゃないですか。でも、飲み比べてみるとモレサンドニの方が美味しいんですよ。それはやっぱり、元々モレサンドニの生産者だからかな、と思っていて。勝沼の人間が穂坂の人間にあんまりいうのは良くない。その人たちの方が土地をわかっているということだから、と考えています。」 ▲ 「リーファーコンテナを使って」とおっしゃっていたので、同機能の何かかと思ったが、本当にリーファーコンテナだ。 必ずしも意図的でないにしても、栽培に関しての自身の介入が少ない。雨宮さんが造るワインに対する評価は、醸造に多くのリソースを注ぐ、まさに醸造家としての彼の実力に与えられたものだろう。しかし、 (マスカット・ベーリーAに関しては) ちんたらやることですね。...

山梨・くらむぼんワイン
日本ワインコラム | 山梨 くらむぼんワイン 「一番の転機は、フランスへ行ったことです。23歳の時に留学をしました。当時は、家業を継ぐこともあまり考えていなくて、弟がいるので、どちらかが継ぐのだろうなぁ、といったような認識でした。」 アイルトン・セナに憧れて、慶応大学理工学部にまで入り、ゆくゆくはルノーでのエンジニアリングライフを見据えていたかどうかは存じ上げないが、ともあれ、野沢たかひこさんは、FW16程に不安定な大学時代に、学歴社会をコースアウトして、南仏へ飛び立った。 ▲ 「森の香りがするんです。」と、自社畑の土を香る野沢さん。わざわざポーズを決めていただいたのに、普通の写真ですみません。レンズ変えるべきでした。 「ニースのホームステイ先で、ワインを毎日出してくれて、それでワインを初めて美味しいと感じました。それまで、日本に美味しいワインってあまりなかったんですよね。元々は親の仕事にも興味がなくワインには関心がなかったのですが、フランスで体験した、家族や友達が集まり、ワインを中心にして人間関係とかが広まっていく、ということを地元の山梨でもやれたらなぁ、と思いました。 大学時代は、授業にも出ていなかったのですが、フランスに行ったら新しい人生の始まりという感じでした。」 煌びやかなニューライフ。周りには、自分のことを知っているものなど誰もいない。地中海を臨み、国籍の違う仲間たちと、夜な夜なワインをボトルで回し飲みする、スーパーモラトリアムな日々。そんな語学学校生活を経て、野沢さんは、ブルゴーニュのCFPPA(ボーヌ農業促進・職業訓練センター)でディプロマを得た。 ▲ 終始朗らかにご対応くださった野沢さん。お迎えいただきありがとうございました。 しかし、意外にも彼が最も影響を受けた生産者として、名前を挙げるのは 「Domaine de Souch」、1987年創業という異端な歴史を持ちながら、ジュランソンを代表すると評される生産者だ。 彼女は夫亡き後、60歳代でワイン造りを始めた、ビオディナミの先駆者の一人 です。彼女の造る「Jurancon sec(辛口)」や「moelleux(甘口)」をタンクから試飲させていただいた時、そのあまりにピュアで、土地の花や土の風味に溢れ、自然な風味でそして幸せな余韻も永く続くワインに、とにかく圧倒されました。これこそがテロワール、いやブドウがある風土がそのままワインに出ていると。もちろん、彼女の人柄がワインに表れていたのは言うまでもありません。 広大な敷地に、荘厳かつ柔らかい空気纏って佇む、養蚕農家を移築したという日本家屋の母屋が印象的な『くらむぼんワイン』。自家醸造の酒蔵として大正2年に創業した同社は、協同組合となって近隣の農家の葡萄からワインを醸造。 ▲ 吹き付ける強風に「ガタガタ」と大きな音を立てる母屋の縁側。夜中にトイレへ行くときは物凄い恐怖感だそうです。 昭和37年から、農家の株を買い取り「有限会社山梨ワイン醸造」が設立。後に株式会社化を経て、2014年、『株式会社くらむぼんワイン』と社名変更がなされた。 野沢たかひこさんは、同社の三代目に当たる。 「フランスから帰国してワイナリーで働き始めた当初は、日本のような雨が多い 気候では農薬を効果的に散布しなければブドウの収穫が出来ないと考えて、叢生 栽培は行っていましたが、化学農薬・肥料は普通に使っていました。」 そういった、謂わば「農家として普通の栽培」を行っていた野沢さんが出会ったのが、福岡正信著作の「自然農法 藁一本の革命」だった。...
山梨・くらむぼんワイン
日本ワインコラム | 山梨 くらむぼんワイン 「一番の転機は、フランスへ行ったことです。23歳の時に留学をしました。当時は、家業を継ぐこともあまり考えていなくて、弟がいるので、どちらかが継ぐのだろうなぁ、といったような認識でした。」 アイルトン・セナに憧れて、慶応大学理工学部にまで入り、ゆくゆくはルノーでのエンジニアリングライフを見据えていたかどうかは存じ上げないが、ともあれ、野沢たかひこさんは、FW16程に不安定な大学時代に、学歴社会をコースアウトして、南仏へ飛び立った。 ▲ 「森の香りがするんです。」と、自社畑の土を香る野沢さん。わざわざポーズを決めていただいたのに、普通の写真ですみません。レンズ変えるべきでした。 「ニースのホームステイ先で、ワインを毎日出してくれて、それでワインを初めて美味しいと感じました。それまで、日本に美味しいワインってあまりなかったんですよね。元々は親の仕事にも興味がなくワインには関心がなかったのですが、フランスで体験した、家族や友達が集まり、ワインを中心にして人間関係とかが広まっていく、ということを地元の山梨でもやれたらなぁ、と思いました。 大学時代は、授業にも出ていなかったのですが、フランスに行ったら新しい人生の始まりという感じでした。」 煌びやかなニューライフ。周りには、自分のことを知っているものなど誰もいない。地中海を臨み、国籍の違う仲間たちと、夜な夜なワインをボトルで回し飲みする、スーパーモラトリアムな日々。そんな語学学校生活を経て、野沢さんは、ブルゴーニュのCFPPA(ボーヌ農業促進・職業訓練センター)でディプロマを得た。 ▲ 終始朗らかにご対応くださった野沢さん。お迎えいただきありがとうございました。 しかし、意外にも彼が最も影響を受けた生産者として、名前を挙げるのは 「Domaine de Souch」、1987年創業という異端な歴史を持ちながら、ジュランソンを代表すると評される生産者だ。 彼女は夫亡き後、60歳代でワイン造りを始めた、ビオディナミの先駆者の一人 です。彼女の造る「Jurancon sec(辛口)」や「moelleux(甘口)」をタンクから試飲させていただいた時、そのあまりにピュアで、土地の花や土の風味に溢れ、自然な風味でそして幸せな余韻も永く続くワインに、とにかく圧倒されました。これこそがテロワール、いやブドウがある風土がそのままワインに出ていると。もちろん、彼女の人柄がワインに表れていたのは言うまでもありません。 広大な敷地に、荘厳かつ柔らかい空気纏って佇む、養蚕農家を移築したという日本家屋の母屋が印象的な『くらむぼんワイン』。自家醸造の酒蔵として大正2年に創業した同社は、協同組合となって近隣の農家の葡萄からワインを醸造。 ▲ 吹き付ける強風に「ガタガタ」と大きな音を立てる母屋の縁側。夜中にトイレへ行くときは物凄い恐怖感だそうです。 昭和37年から、農家の株を買い取り「有限会社山梨ワイン醸造」が設立。後に株式会社化を経て、2014年、『株式会社くらむぼんワイン』と社名変更がなされた。 野沢たかひこさんは、同社の三代目に当たる。 「フランスから帰国してワイナリーで働き始めた当初は、日本のような雨が多い 気候では農薬を効果的に散布しなければブドウの収穫が出来ないと考えて、叢生 栽培は行っていましたが、化学農薬・肥料は普通に使っていました。」 そういった、謂わば「農家として普通の栽培」を行っていた野沢さんが出会ったのが、福岡正信著作の「自然農法 藁一本の革命」だった。...

山梨・機山洋酒工業
日本ワインコラム | 山梨 機山洋酒工業 「こだわりってね、僕はないんですよ。 若い頃なんか取材でこだわりはなんですかなんて聞かれると、頭にきて、帰れ、とか言っちゃったりしてね。」 率直にいう。私は困った。 ▲ 機山洋酒工業の何から何までをお二人で手掛ける土屋ご夫妻。同じ大学を出られて、国税庁醸造試験所でもご一緒だったそうです。 日本ワインへの造詣が深くないことを半ばコンプレックス気味に自負している筆者にとって、生産者の方々の「こだわり」は、コラムを書く上で、最も容易かつ明解かつ差別化しやすく、深掘りしやすい大事な切り口である。だから、私は洗練されていようが歪であろうが、「こだわり」を要請してきた。 ▲ 気さくに取材に応じてくださった土屋さん。時折挟まれる「いい話でしょ~!?」という念押しが記憶に残っています。筆者は果たして、「いい話」を、いい話として書き下せたのだろうか。 こだわりって、元々の意味で言うと「とらわれている」ような否定的な意味だと思うのですが、僕には、どうしてもこうじゃないといけないってものがないんですよ。例えば「甲州に拘っているじゃないか」と言われることもあるのですが、それは拘っているわけではありません。(気候土壌への適性だけでなく、歴史的な背景など)あらゆる意味合いで、甲州より優れた品種があるのなら、それは変えていきますよ。今、それがないというだけです。 「スマート」というと軽いだろうか、「理知的」というと形式ばって響くだろうか、軽快に慎重に、外交的に内省的に、朗らかに強かに。 その軽微なアンビバテントは、彼が作るワインにも通底したものがあるような気がしている。安いのに旨い、という話ではない。工業的な緻密性で、クラフト的なテイを有しているという意味においてだ。 ▲ フンコロガシをデザインした、かつての機山洋酒工業のエンブレム 山梨県甲州市塩山。日本三大急流にも数えられる富士川へと流れ込む笛吹川の脇、機山洋酒工業は、北東から南西に太平洋へ向かうこの一級河川によって形成された河岸段丘の上に位置するワイナリーだ。 「(先々代は)元々、石炭業を営んでいました。というのも、山梨においては養蚕が盛んな地域で製糸工業が重要な産業でした。絹糸を手繰る際に高温の水が必要なのですが、その熱源となったのが石炭だったのです。」 石炭業からワイン製造への転換の契機となったのは、昭和5年の世界恐慌。世界経済が急激に冷え込んだことによって、輸出産業としての比重が大きかった製糸工業は衰退し、石炭の需要も急落した。 ▲ 直売スペースには、ワインボトルから造られたグラスやミニボトルがしつらえられている。 そういった状況で、養蚕に代わる産業として注目を集めたのがワイン造りでした。 先々代もその産業の遷移の流れに乗り、ワイン造りを始めた。当時3,000もの零細生産者が生まれるほどに勃興したワイン産業だが、その殆どが今は見る影もない。その中で生き残り、現在まで引き継がれているのが機山洋酒工業だ。 三代目の土屋幸三さんは、メーカーの研究員としての6年のキャリアを経て、1994年の8月に会社を辞め、ワイン造りの家業を継いだ。 元々は街の電気屋さんになりたかったので、(大学は)電気とか通信の学科に行こうと思っていました。ですが、父にその話をすると、 「お前、後継ぐんだろ。」なんて言われてしまいまして。「ダメ」っていうならしょうがないなぁ、なんて思いながら調べたら、その当時は、電気通信の学科と醗酵学科の二次試験の科目が同じだったのです。 1980年代のバイオテクノロジー・ブーム。石油・石炭を燃料・原料とした大量消費と爆発的な成長から、微生物や遺伝子組み替えを媒介した、クリーンで省エネルギーな、より緻密な科学によって興される未来が描かれた時代だ。「アマチュア無線免許」まで取得していた電子工作青年だったという土屋さんだが、その時代を象徴すると言える大阪大学醗酵学科で学問を修め、バイオケミカル事業を手がける企業へ就職した。 ▲ こんなにお値打ちで、こんなに美味しいのですが、まだまだ整然に積み重ねられた在庫が。...
山梨・機山洋酒工業
日本ワインコラム | 山梨 機山洋酒工業 「こだわりってね、僕はないんですよ。 若い頃なんか取材でこだわりはなんですかなんて聞かれると、頭にきて、帰れ、とか言っちゃったりしてね。」 率直にいう。私は困った。 ▲ 機山洋酒工業の何から何までをお二人で手掛ける土屋ご夫妻。同じ大学を出られて、国税庁醸造試験所でもご一緒だったそうです。 日本ワインへの造詣が深くないことを半ばコンプレックス気味に自負している筆者にとって、生産者の方々の「こだわり」は、コラムを書く上で、最も容易かつ明解かつ差別化しやすく、深掘りしやすい大事な切り口である。だから、私は洗練されていようが歪であろうが、「こだわり」を要請してきた。 ▲ 気さくに取材に応じてくださった土屋さん。時折挟まれる「いい話でしょ~!?」という念押しが記憶に残っています。筆者は果たして、「いい話」を、いい話として書き下せたのだろうか。 こだわりって、元々の意味で言うと「とらわれている」ような否定的な意味だと思うのですが、僕には、どうしてもこうじゃないといけないってものがないんですよ。例えば「甲州に拘っているじゃないか」と言われることもあるのですが、それは拘っているわけではありません。(気候土壌への適性だけでなく、歴史的な背景など)あらゆる意味合いで、甲州より優れた品種があるのなら、それは変えていきますよ。今、それがないというだけです。 「スマート」というと軽いだろうか、「理知的」というと形式ばって響くだろうか、軽快に慎重に、外交的に内省的に、朗らかに強かに。 その軽微なアンビバテントは、彼が作るワインにも通底したものがあるような気がしている。安いのに旨い、という話ではない。工業的な緻密性で、クラフト的なテイを有しているという意味においてだ。 ▲ フンコロガシをデザインした、かつての機山洋酒工業のエンブレム 山梨県甲州市塩山。日本三大急流にも数えられる富士川へと流れ込む笛吹川の脇、機山洋酒工業は、北東から南西に太平洋へ向かうこの一級河川によって形成された河岸段丘の上に位置するワイナリーだ。 「(先々代は)元々、石炭業を営んでいました。というのも、山梨においては養蚕が盛んな地域で製糸工業が重要な産業でした。絹糸を手繰る際に高温の水が必要なのですが、その熱源となったのが石炭だったのです。」 石炭業からワイン製造への転換の契機となったのは、昭和5年の世界恐慌。世界経済が急激に冷え込んだことによって、輸出産業としての比重が大きかった製糸工業は衰退し、石炭の需要も急落した。 ▲ 直売スペースには、ワインボトルから造られたグラスやミニボトルがしつらえられている。 そういった状況で、養蚕に代わる産業として注目を集めたのがワイン造りでした。 先々代もその産業の遷移の流れに乗り、ワイン造りを始めた。当時3,000もの零細生産者が生まれるほどに勃興したワイン産業だが、その殆どが今は見る影もない。その中で生き残り、現在まで引き継がれているのが機山洋酒工業だ。 三代目の土屋幸三さんは、メーカーの研究員としての6年のキャリアを経て、1994年の8月に会社を辞め、ワイン造りの家業を継いだ。 元々は街の電気屋さんになりたかったので、(大学は)電気とか通信の学科に行こうと思っていました。ですが、父にその話をすると、 「お前、後継ぐんだろ。」なんて言われてしまいまして。「ダメ」っていうならしょうがないなぁ、なんて思いながら調べたら、その当時は、電気通信の学科と醗酵学科の二次試験の科目が同じだったのです。 1980年代のバイオテクノロジー・ブーム。石油・石炭を燃料・原料とした大量消費と爆発的な成長から、微生物や遺伝子組み替えを媒介した、クリーンで省エネルギーな、より緻密な科学によって興される未来が描かれた時代だ。「アマチュア無線免許」まで取得していた電子工作青年だったという土屋さんだが、その時代を象徴すると言える大阪大学醗酵学科で学問を修め、バイオケミカル事業を手がける企業へ就職した。 ▲ こんなにお値打ちで、こんなに美味しいのですが、まだまだ整然に積み重ねられた在庫が。...

栃木・ココファーム・ワイナリー
日本ワインコラム | 関東・栃木 ココ・ファーム・ワイナリー 我々は一般に 「優れた葡萄産地にあるワイナリーで、優れたワインは造られる。」 と考えることを好む傾向にある。 「ロンドンにある自社畑のリースリングからワイン造りました。」 「ブルゴーニュのピノ・ノワールをパリで醸造しました。」 なんて言われても、なんだか得心がいかない。どんなに完璧な味わいでも、「何か入れてるんじゃないの?」なんて不確かなことを言い始めるのがオチで、どうにも腑に落ちないのである。おそらく。 ▲ 急斜面・強風という状況下でも、こころみ学園の園生は休まず畑に立っている。 欧州を例に出した。日本の場合はどうだろう。 「北海道の葡萄を北海道でワインにしました。」 「山形県の葡萄を山形県でワインにしました。」 いわゆるドメーヌだ。 優れた産地が生んだ葡萄が、その優れた産地でワインになる。 では、これはどうだろう。 「北海道の葡萄を栃木県でワインにする。」 「山梨県の葡萄を栃木県でワインにする。」 栃木県は北関東で、山梨県は中部、あるいは南関東で、北海道は言うまでもない。パリとブルゴーニュの距離の例はさほど大袈裟ではない。 これはどうか。 「栃木県の葡萄を栃木県でワインにする。」 ▲ 元々は松が自生するようなやせた土壌を、川田昇さんが切り拓いた。 栃木県が葡萄の産地として知られているかといえばそうではない。ロンドンの例は流石に誇張だが、実際に葡萄生産量では全国上位10番までにも入っていない。名産と言えば「とちおとめ」「餃子」「レモン牛乳」。「とちおとめ」は果実だが葡萄ではないし、「餃子」は皮と身があっても果実じゃない。「レモン牛乳」はもうよくわからない。 ▲ リースリング・リオンとは思えないほどの厚みと奥行をもった「 のぼ ブリュット...
栃木・ココファーム・ワイナリー
日本ワインコラム | 関東・栃木 ココ・ファーム・ワイナリー 我々は一般に 「優れた葡萄産地にあるワイナリーで、優れたワインは造られる。」 と考えることを好む傾向にある。 「ロンドンにある自社畑のリースリングからワイン造りました。」 「ブルゴーニュのピノ・ノワールをパリで醸造しました。」 なんて言われても、なんだか得心がいかない。どんなに完璧な味わいでも、「何か入れてるんじゃないの?」なんて不確かなことを言い始めるのがオチで、どうにも腑に落ちないのである。おそらく。 ▲ 急斜面・強風という状況下でも、こころみ学園の園生は休まず畑に立っている。 欧州を例に出した。日本の場合はどうだろう。 「北海道の葡萄を北海道でワインにしました。」 「山形県の葡萄を山形県でワインにしました。」 いわゆるドメーヌだ。 優れた産地が生んだ葡萄が、その優れた産地でワインになる。 では、これはどうだろう。 「北海道の葡萄を栃木県でワインにする。」 「山梨県の葡萄を栃木県でワインにする。」 栃木県は北関東で、山梨県は中部、あるいは南関東で、北海道は言うまでもない。パリとブルゴーニュの距離の例はさほど大袈裟ではない。 これはどうか。 「栃木県の葡萄を栃木県でワインにする。」 ▲ 元々は松が自生するようなやせた土壌を、川田昇さんが切り拓いた。 栃木県が葡萄の産地として知られているかといえばそうではない。ロンドンの例は流石に誇張だが、実際に葡萄生産量では全国上位10番までにも入っていない。名産と言えば「とちおとめ」「餃子」「レモン牛乳」。「とちおとめ」は果実だが葡萄ではないし、「餃子」は皮と身があっても果実じゃない。「レモン牛乳」はもうよくわからない。 ▲ リースリング・リオンとは思えないほどの厚みと奥行をもった「 のぼ ブリュット...
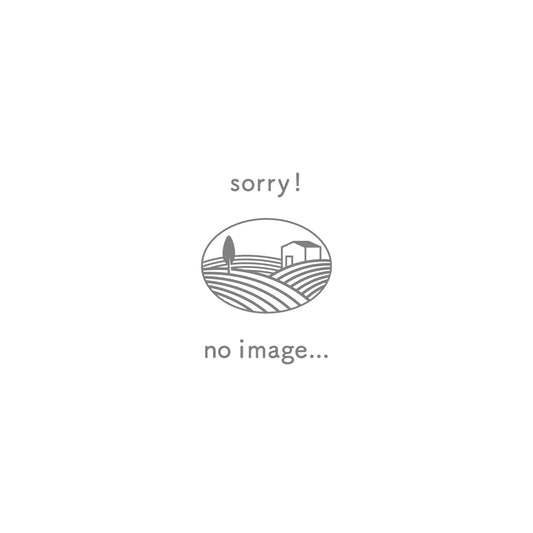
中四国のワイナリー
中四国のワイナリー 中四国はワインの産地としてはそれほど名が通っていないかもしれません。しかし現在、このエリアの9県全てで日本ワインが生産されています。 この中で最も生産量が多いのが岡山県。元々、ハウス栽培の生食用マスカットで定評のある県で、大手ビールメーカーのワイナリーもありますが、 現在は新見市などの内陸部にワイナリーの設立が続いています。 中でも日本では珍しいテラロッサの土壌でぶどうを栽培するDomaine Tettaは海外からも注目されており、ナチュラルなアプローチで滋味深いワインを生むコルトラーダなども興味深いワインをつくります。 倉敷市のGRAPE SHIPなど、元々の名産であるマスカット・オブ・アレキサンドリアを活かしたワインづくりを行う生産者も出て来ています。 お隣の広島県でも内陸部を中心にワインが生産されています。広島三次ワイナリーが有名ですが、他にも海外のコンクールで金賞を受賞するようなワイナリーも登場して来ています。広島県の内陸部は高品質なシャルドネに定評があります。山陰側では島根県が独自の魅力を放っています。実は山梨県の次に甲州の生産量が多い都道府県は島根県(とは言え全国シェア2.5%程度ですが)。出雲大社の畔で内陸の山梨とはまた異なる柔らかな味わいの甲州が生まれています。 また、内陸に入った木次では木次乳業のグループ会社である奥出雲葡萄園が小公子やシャルドネから魅力的なワインを生んでいます。 お隣の鳥取県は砂丘で有名ですが、砂丘近くでぶどうが栽培されており、砂質ならではの香り高いワインが生産されています。 中国地方の最後、山口県のワイナリーはまだまだ少ないですが、瀬戸内海の島でもワインづくりが始まっています。四国のワイナリー数は2022年末の統計で4県計で10軒。高知と香川に3軒ずつ、愛媛と徳島に2軒ずつです。高知県は暑く、秋の台風の影響も受けやすい県ですが、萌芽から収穫までの生産サイクルが他県よりも早く、台風の影響は限定的です。ボルドー液の生産会社が立ち上げた(=石灰質土壌の)ワイナリーが興味深いワインを生産しています。アルバリーニョも注目したいところ。 その他の県でも新規のワイナリーの設立が続いていますが、まだ県の特徴や象徴的なぶどう品種と言ったものが生まれる状況ではありません。生食用ぶどうも交えつつ、安定的なぶどう生産を目指すワイナリーが多いです。比較的天候が安定している、小豆島などの瀬戸内の島々でのワイン生産も増えています。 中四国編 NEW ! NEW ! NEW ! NEW ! その他の中四国のワイン
中四国のワイナリー
中四国のワイナリー 中四国はワインの産地としてはそれほど名が通っていないかもしれません。しかし現在、このエリアの9県全てで日本ワインが生産されています。 この中で最も生産量が多いのが岡山県。元々、ハウス栽培の生食用マスカットで定評のある県で、大手ビールメーカーのワイナリーもありますが、 現在は新見市などの内陸部にワイナリーの設立が続いています。 中でも日本では珍しいテラロッサの土壌でぶどうを栽培するDomaine Tettaは海外からも注目されており、ナチュラルなアプローチで滋味深いワインを生むコルトラーダなども興味深いワインをつくります。 倉敷市のGRAPE SHIPなど、元々の名産であるマスカット・オブ・アレキサンドリアを活かしたワインづくりを行う生産者も出て来ています。 お隣の広島県でも内陸部を中心にワインが生産されています。広島三次ワイナリーが有名ですが、他にも海外のコンクールで金賞を受賞するようなワイナリーも登場して来ています。広島県の内陸部は高品質なシャルドネに定評があります。山陰側では島根県が独自の魅力を放っています。実は山梨県の次に甲州の生産量が多い都道府県は島根県(とは言え全国シェア2.5%程度ですが)。出雲大社の畔で内陸の山梨とはまた異なる柔らかな味わいの甲州が生まれています。 また、内陸に入った木次では木次乳業のグループ会社である奥出雲葡萄園が小公子やシャルドネから魅力的なワインを生んでいます。 お隣の鳥取県は砂丘で有名ですが、砂丘近くでぶどうが栽培されており、砂質ならではの香り高いワインが生産されています。 中国地方の最後、山口県のワイナリーはまだまだ少ないですが、瀬戸内海の島でもワインづくりが始まっています。四国のワイナリー数は2022年末の統計で4県計で10軒。高知と香川に3軒ずつ、愛媛と徳島に2軒ずつです。高知県は暑く、秋の台風の影響も受けやすい県ですが、萌芽から収穫までの生産サイクルが他県よりも早く、台風の影響は限定的です。ボルドー液の生産会社が立ち上げた(=石灰質土壌の)ワイナリーが興味深いワインを生産しています。アルバリーニョも注目したいところ。 その他の県でも新規のワイナリーの設立が続いていますが、まだ県の特徴や象徴的なぶどう品種と言ったものが生まれる状況ではありません。生食用ぶどうも交えつつ、安定的なぶどう生産を目指すワイナリーが多いです。比較的天候が安定している、小豆島などの瀬戸内の島々でのワイン生産も増えています。 中四国編 NEW ! NEW ! NEW ! NEW ! その他の中四国のワイン

山形・朝日町ワイン
日本ワインコラム | 東北・山形 朝日町ワイン 18歳の頃から41年間、朝日町ワインに人生を捧げてきた 「ミスター・叩き上げ」 現在は取締役・営業本部長を務める近衛秀敏さんは、自らのモットーに、同社の信条を引用する。自身の生き方そのものが、勤務する会社の信条にぴったりと重なるという現象はあまり一般的ではないはずだが、製造から営業までほとんど全ての職務を経験している近衛さんにとって、その一致は自然なことなのかもしれない。 ▲ 平地部のマスカット・ベーリーA 一文字長梢選定。長く伸ばした梢を幹のほうに誘引して、先端部に結実する良質なブドウ 「会社とご自身で同じなんですか。」という問いにも、「そうですね。」の一言である。そうですか。と言うしかない。朝日町ワインと言えば、「価格は控えめながら、安定して高い品質のワイン」というイメージが漠然とでも浮かぶのではないだろうか。近衛さんは、そんな同社に対する、安心・信頼を築き上げた立役者の一人だ。工場長の任を解かれて、営業として各地を回るようになってからも、現場の指導を続け、2代に渡って現場責任者の育成に努めてきた。 私自身はもうワインを作っていなくて、15,6年前から、それまで会社になかった営業職をやっています。(加えて)私たちはチームですから、個人がワイン造りのすべてを決めてきたということはないんです。 ▲ 一文字短梢選定ハヤシスマート法の改良モデル。母枝を一方向のみに残すことで、収量を増やす効果があるそう。 仮に私なら「俺が造った。」ぐらいのことを吹聴しそうなものであるが、いや待て、そういう疾しい人間はそもそも「まじめに」造れないのである。やはり仕事と背中で語る昭和の勤め人的ハードボイルドを纏った近衛さんの存在をして、現在のワイナリーの地位の確立があるのだろう。 さて、朝日町は、山形県中央部、新潟県との県境を構成する朝日連峰の主峰、大朝日岳の東部山麓地域に位置する。最上川の急流が南北21kmにわたり蛇行する町内は、そのの76%が山林に覆われ、何処を見渡しても自然が立ちはだかる。それも雄大なタイプの。 ▲ 一文字短梢選定は、枝の位置が規則的で大変歩きやすい。 山河に埋め尽くされたこの土地には、最上川が形成する河岸段丘の傾斜地が多くみられる。「河岸段丘」という単語から「果樹園」を条件反射的に導けないようでは、受験生失格。2013年にも地理Bにて出題されているように最上川流域では、その段丘を利用した果樹栽培が活発なのである。 ともあれ、この朝日町も豊富な段丘面にリンゴ、ブドウをはじめとした果樹園が広がっている。町の特産物は「無袋(むたい)ふじ」という、果実に保護用の袋をかぶせずに栽培されるふじリンゴ。有袋類とは呼ばないだろうが、袋を被ったリンゴに比べてより甘みが増すという。近衛さんのご実家もリンゴ農家だそうだ。「リンゴとワインの里」たる朝日町で、リンゴ農家に生まれ、41年間ワイナリーに務めている近衛さん。もはや町が歩いているようなものである。 ▲ 柏原ヴィンヤード。山砂の多い痩せた土壌であるため、平地部のブドウと比較して、枝が長く伸びにくいのだそう。最高樹齢は開墾時の植樹の46年 さて、朝日町ワインの設立は昭和19年にまでさかのぼる。 当時、日本政府はワインの成分の酒石酸から、電波探知機の圧電素子に使う軍需物資「ロッシェル塩(酒石酸カリウムナトリウム)」を取り出すことを目的に、全国のブドウ産地に命じてワイン工場を造らせた。それによって、山梨県や山形県などの果樹産地に軍の保護を受けたワイン工場が多く誕生したが、その一つが朝日町ワインの前身となる「山形果実酒製造有限会社」だった。 より有効な材料が発見されたことで、圧電素子としてのロッシェル塩は次第に姿を消し、軍需物質の生産という役割が失われて以降は、甘口ワインブームから需要が高まっていたポートワインの原料となる赤ワインを、大手メーカーへ供給することが主な事業となった。 しかし、昭和50年ころから甘口ワインの需要が衰退し、メーカーからの受注もなくなっていく。またしても供給先を失った状況。そんな中で、ブドウ農家を守るため、山形朝日農協と朝日町が共同出資し、第三セクター方式の会社運営へと転換した。着眼したのは、ポートワインの原料として、町内に多く作付けされていたマスカット・ベーリーA。朝日町ワインは、この品種での「日本一」を目指し、品質にこだわった「まじめなワイン造り」をスタートさせた。 ▲ 標高330mの柏原ヴィンヤードは、非常に冷涼で雪も積もりやすい。向こうに見えるのは、最上川の対岸の河岸段丘 現在は11.3haにも及ぶ朝日町町内の契約農家の畑、そして、自社工場である朝日町ワイン城の前に広がる0.7haの自社畑から年間35万本のワインを生み出す、日本でも指折りの規模のワイナリーとなっている。 起伏の激しい地形である朝日町には、マスカット・ベーリーAの畑だけでも、標高110m~330m、最上川の河岸から山の上まで様々な立地が存在する。その中で、マスカット・ベーリーAという品種での日本一を目指す当ワイナリーにおいて、最も注目され、道中、近衛さんが最も誇らしげに紹介したのが「柏原ヴィンヤード」だ。...
山形・朝日町ワイン
日本ワインコラム | 東北・山形 朝日町ワイン 18歳の頃から41年間、朝日町ワインに人生を捧げてきた 「ミスター・叩き上げ」 現在は取締役・営業本部長を務める近衛秀敏さんは、自らのモットーに、同社の信条を引用する。自身の生き方そのものが、勤務する会社の信条にぴったりと重なるという現象はあまり一般的ではないはずだが、製造から営業までほとんど全ての職務を経験している近衛さんにとって、その一致は自然なことなのかもしれない。 ▲ 平地部のマスカット・ベーリーA 一文字長梢選定。長く伸ばした梢を幹のほうに誘引して、先端部に結実する良質なブドウ 「会社とご自身で同じなんですか。」という問いにも、「そうですね。」の一言である。そうですか。と言うしかない。朝日町ワインと言えば、「価格は控えめながら、安定して高い品質のワイン」というイメージが漠然とでも浮かぶのではないだろうか。近衛さんは、そんな同社に対する、安心・信頼を築き上げた立役者の一人だ。工場長の任を解かれて、営業として各地を回るようになってからも、現場の指導を続け、2代に渡って現場責任者の育成に努めてきた。 私自身はもうワインを作っていなくて、15,6年前から、それまで会社になかった営業職をやっています。(加えて)私たちはチームですから、個人がワイン造りのすべてを決めてきたということはないんです。 ▲ 一文字短梢選定ハヤシスマート法の改良モデル。母枝を一方向のみに残すことで、収量を増やす効果があるそう。 仮に私なら「俺が造った。」ぐらいのことを吹聴しそうなものであるが、いや待て、そういう疾しい人間はそもそも「まじめに」造れないのである。やはり仕事と背中で語る昭和の勤め人的ハードボイルドを纏った近衛さんの存在をして、現在のワイナリーの地位の確立があるのだろう。 さて、朝日町は、山形県中央部、新潟県との県境を構成する朝日連峰の主峰、大朝日岳の東部山麓地域に位置する。最上川の急流が南北21kmにわたり蛇行する町内は、そのの76%が山林に覆われ、何処を見渡しても自然が立ちはだかる。それも雄大なタイプの。 ▲ 一文字短梢選定は、枝の位置が規則的で大変歩きやすい。 山河に埋め尽くされたこの土地には、最上川が形成する河岸段丘の傾斜地が多くみられる。「河岸段丘」という単語から「果樹園」を条件反射的に導けないようでは、受験生失格。2013年にも地理Bにて出題されているように最上川流域では、その段丘を利用した果樹栽培が活発なのである。 ともあれ、この朝日町も豊富な段丘面にリンゴ、ブドウをはじめとした果樹園が広がっている。町の特産物は「無袋(むたい)ふじ」という、果実に保護用の袋をかぶせずに栽培されるふじリンゴ。有袋類とは呼ばないだろうが、袋を被ったリンゴに比べてより甘みが増すという。近衛さんのご実家もリンゴ農家だそうだ。「リンゴとワインの里」たる朝日町で、リンゴ農家に生まれ、41年間ワイナリーに務めている近衛さん。もはや町が歩いているようなものである。 ▲ 柏原ヴィンヤード。山砂の多い痩せた土壌であるため、平地部のブドウと比較して、枝が長く伸びにくいのだそう。最高樹齢は開墾時の植樹の46年 さて、朝日町ワインの設立は昭和19年にまでさかのぼる。 当時、日本政府はワインの成分の酒石酸から、電波探知機の圧電素子に使う軍需物資「ロッシェル塩(酒石酸カリウムナトリウム)」を取り出すことを目的に、全国のブドウ産地に命じてワイン工場を造らせた。それによって、山梨県や山形県などの果樹産地に軍の保護を受けたワイン工場が多く誕生したが、その一つが朝日町ワインの前身となる「山形果実酒製造有限会社」だった。 より有効な材料が発見されたことで、圧電素子としてのロッシェル塩は次第に姿を消し、軍需物質の生産という役割が失われて以降は、甘口ワインブームから需要が高まっていたポートワインの原料となる赤ワインを、大手メーカーへ供給することが主な事業となった。 しかし、昭和50年ころから甘口ワインの需要が衰退し、メーカーからの受注もなくなっていく。またしても供給先を失った状況。そんな中で、ブドウ農家を守るため、山形朝日農協と朝日町が共同出資し、第三セクター方式の会社運営へと転換した。着眼したのは、ポートワインの原料として、町内に多く作付けされていたマスカット・ベーリーA。朝日町ワインは、この品種での「日本一」を目指し、品質にこだわった「まじめなワイン造り」をスタートさせた。 ▲ 標高330mの柏原ヴィンヤードは、非常に冷涼で雪も積もりやすい。向こうに見えるのは、最上川の対岸の河岸段丘 現在は11.3haにも及ぶ朝日町町内の契約農家の畑、そして、自社工場である朝日町ワイン城の前に広がる0.7haの自社畑から年間35万本のワインを生み出す、日本でも指折りの規模のワイナリーとなっている。 起伏の激しい地形である朝日町には、マスカット・ベーリーAの畑だけでも、標高110m~330m、最上川の河岸から山の上まで様々な立地が存在する。その中で、マスカット・ベーリーAという品種での日本一を目指す当ワイナリーにおいて、最も注目され、道中、近衛さんが最も誇らしげに紹介したのが「柏原ヴィンヤード」だ。...