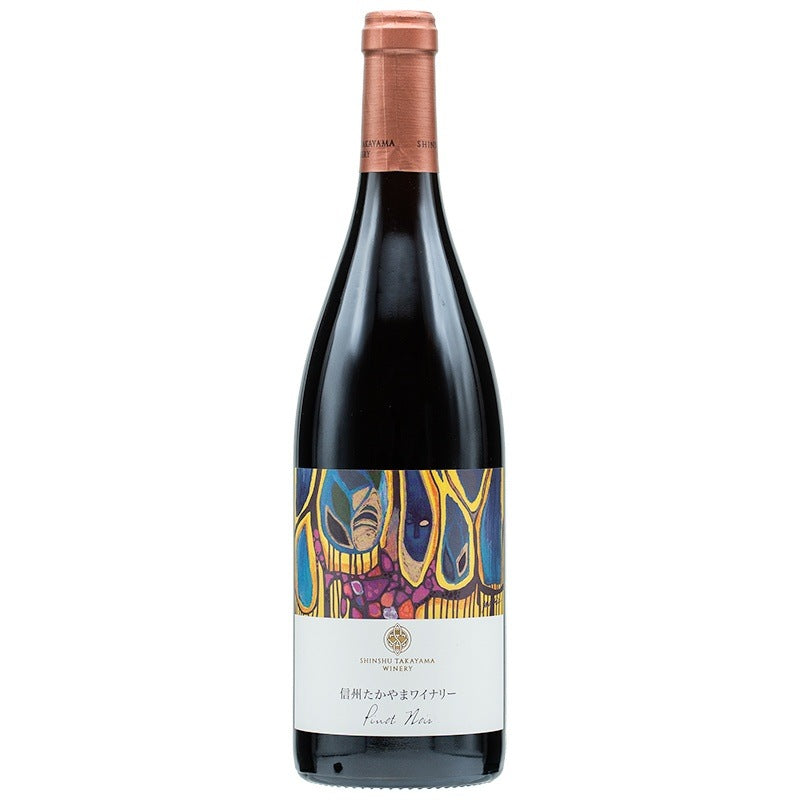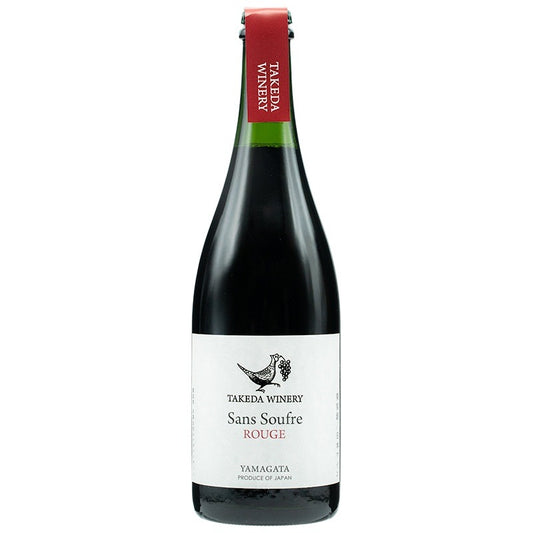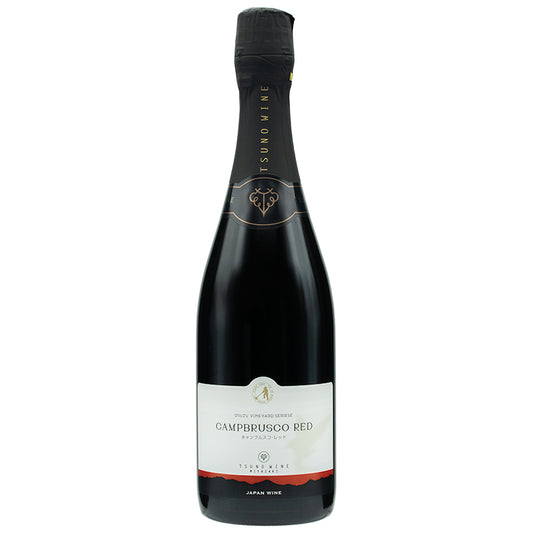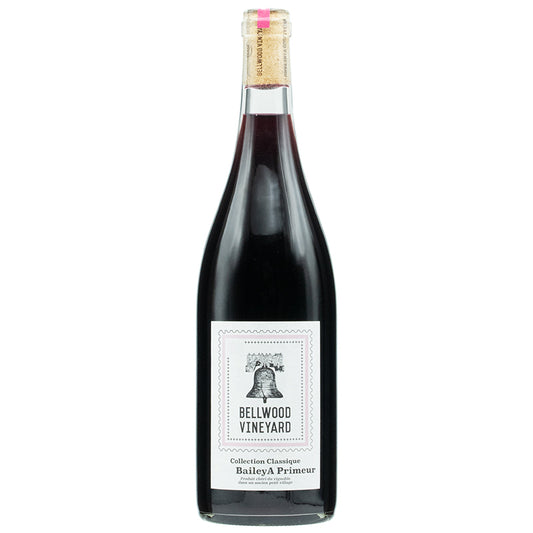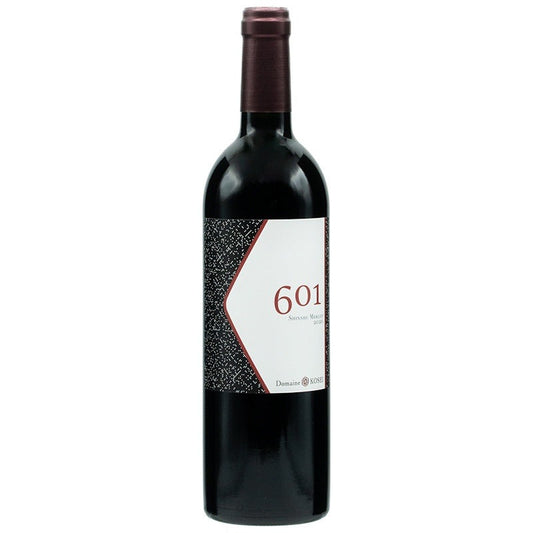1996年より、醸造用の葡萄栽培が始まった高山村。「この地域でならば、世界に通用する葡萄が作れる」。隣接する地域で、長く醸造用葡萄の栽培に携わる角藤農園の佐藤宗一さんや、小布施ワイナリーによる熱心な働きかけによって、それは実現した。2004年には、村内外の意欲的な栽培家や有識者が中心となって、「高山村ワインぶどう研究会」が発足。前村長の協力もあり、遊休耕作地の再生をはじめ、海外研修など精力的な活動を続け、栽培面積は拡大。大手酒造メーカーへの葡萄の供給を行い、その品質は高く評価され、「高山村」のネームバリューは、大きな躍進を見せた。 鷹野さんが高山村の地を踏んだのは、そんな発展の最中だった。
 ▲
高山村に醸造用葡萄を広めた第一人者佐藤宗一さんが栽培を担う角藤農園。
▲
高山村に醸造用葡萄を広めた第一人者佐藤宗一さんが栽培を担う角藤農園。
山梨大学工学部発酵生産学科で学問を修めたのちに、大手酒造メーカーで醸造技術者として長くキャリアを積み、「高山村」の原料も多く扱った経験を持つ鷹野さん。 高山村は、そんな優れたキャリアを有する彼を、ワインに関する業務を専門的に行う任期付き職員として採用した。
 ▲
ワイン醸造の専門職員として鷹野さんが務めた高山村役場。「まさかこの年で地方公務員になるとは思っていなかった」と鷹野さん。
▲
ワイン醸造の専門職員として鷹野さんが務めた高山村役場。「まさかこの年で地方公務員になるとは思っていなかった」と鷹野さん。
 ▲
信州たかやまワイナリーは、高山村の中でも比較的標高の高い傾斜地に位置している。
▲
信州たかやまワイナリーは、高山村の中でも比較的標高の高い傾斜地に位置している。
彼が任期中に取り組んだものとして、あげてくださったのが「ICT気象観測器の設置」だ。村内6箇所に設置された観測器は、気象データを収集、集積し、高山村の気候における特殊なキャラクターを示してくれた。
村内の葡萄畑が広がる領域だけでも、標高400~830mと高低差に富んだ地形である高山村。標高の低いところの気候区分はイタリア南部、高いところではシャンパ―ニュやドイツに相当する特異な土地であった。
「小さな地域
の中で、同じ品種でも酸の高低をはじめ、異なる味わいの個性を持った葡萄が取れるということは、大きなアドバンテージと言えます。
それらをアッサンブラージュしてワインを作ることが出来るのは、国内でも稀なケースと言えるかも知れません。」
栽培地の拡大や気象データの集積、栽培技術の向上など、「高山村ワインぶどう研究会」と自治体の取り組みにより、96年以降、醸造用葡萄栽培地として目覚ましい発展を遂げてきた高山村だが、依然それらの葡萄は外部のワイナリーへ供給される一途をたどっており、村内でのワインの生産は実現に至っていなかった。そんな中、「葡萄産地」から、「ワイン産地」へという新たなステージへの移行を志し、 13人の栽培家を中心に、酒販店や旅館などの出資によって、2016年、「信州たかやまワイナリー」は設立された。そのスローガンともいえるキーワードが、「ワイン産地の形成」だ。長野県というと、既に国内での認知も高く、「ワイン産地」と呼んで相違ないとも思われる地域ではあるが、まだまだ栽培から醸造、ワイナリー経営のノウハウを備えた人材を育成していく必要があり、現状5軒ある同村内のワイナリー数も更に増加していくことが見込まれる。。鷹野さんは、その先駆けとも言えるかたちで設立された「信州たかやまワイナリー」で、取締役執行役員、醸造責任者を努めている。
 ▲
ワイナリーは傾斜地の利点を活かし、葡萄のレセプションが高い位置に来るよう設計されている。曰く「なんちゃってグラビティ・フロー」
▲
ワイナリーは傾斜地の利点を活かし、葡萄のレセプションが高い位置に来るよう設計されている。曰く「なんちゃってグラビティ・フロー」
ワインという「瓶内熟成が価値を生む」稀有な飲料に関し、その「旅立ち」とも言える瓶詰の行程には重点が置かれる。瓶詰室は、微細なフィルターを備えた通気口から清浄な外気を取り込むことで、わずかに加圧され、外部から異物が混入する事のないような設計がなされる。 また、醸造施設内部には捕虫器が設置され、昆虫の混入をモニタリングできるようにもなっている。
「日常的に上質なものを飲んでもらいたい。
それが後世に対して恥ずかしくない基準を保ちながら積み重なっていくこと。イノベーションは、不連続的なものの中から生まれ、現在未来の人類にとって尊いものではありますが、一方で脈々と紡がれた歴史を重ねの中から、本質として残していくべきものもあります。ワインには豊かな多様性がありつつもその中央にあるもの、芯となるもの、そういったものを造り続けていきたいと思っています。」
後世に残せるワイン。回答の端々に長期的な視野を含ませる鷹野さんの語り口から、昨今、品質の高いワインが多くみられることとは別の視点で、日本ワインは産業としていまだ黎明期を出ていないことを強く感じる。