日本ワインコラム
THE CELLAR ワイン特集
長野・ヴェンティクワットロ
日本ワインコラム | ヴェンティクワットロ 長野県須坂市にあるブドウ畑にやってきた。2019年4月に東京から移住してきた西舘さんが管理する畑だ。 屋号はVENTIQUATTRO(ヴェンティクワットロ)。イタリア語で数字の「24」を意味する。イタリアワイン好き×「24」時間(=1日)を大切に、楽しくワインを、という想い×ご自身の苗字である西舘の西(「24」)の掛け合わせにより、この名称を選んだそう。 ▲ 取材の後日、西舘さんから頂いた畑の様子。青空と遠目に見える山々、そして畑の緑が美しい。実は、訪問日は前日から続く黄砂の影響ですっきりしない空模様且つ強風…取材中にメモ用紙が強風で吹き飛ばされ、畑中を皆で駆け回って回収するという珍プレーが…お騒がせ致しました(汗)。 西舘さんがこの地でブドウ栽培を始めるまでに、いくつもの人との出会いがある。ある出会いが次の出会いに繋がり、何かに導かれるように今、この地に立っているのだ。 動かないと始まらない 西舘さんは長い間、東京の出版業界にいた。20代の頃からワイン好きだったが、仕事とは別物として捉えてきたのだ。顧客訪問中のある時、御徒町の雑居ビルにワイナリーを発見。「こんな街中にワイナリーが⁉」と驚き、色々と話を聞く中で、これまでずっと蓋をしてきた「自分でワインを造ってみたい」という淡い夢が現実味を帯びてきた。 さて、ここからが西舘さんの凄いところ。可能性を感じたら、とにかく動く。そして自分の目で確かめる。この凄さをご理解頂くために、西舘さんの足取りを紹介したい。 ▲ 今回の取材相手の西舘さん。目じりが下がり気味の優しい笑顔をまとい、いい感じに肩の力が抜けた様子で周りの農家の方と会話をする姿が印象的。回遊魚のように動き回っているとは信じられない物腰だ。 まず、色々調べた中で話を聞いてみたいと思った新潟県のワイナリーを訪問する。そこでの研修内容は自分の希望条件と合わなかったが、先方から長野県が主催する「ワイン生産アカデミー」を受講してみてはどうかとアドバイスがあった。調べてみると受付終了の2週間前で、即座に申し込む。因みに、講座の開催場所は、現在西舘さんの畑がある須坂市だった。振り返ってみると縁を感じるセッティングだ。 受講を終え、近くのワインバーにふらっと入り、グラスワインとして提供されたイタリア品種のアリアニコを使った赤ワインにビビっと来た。実は、以前、とあるイタリアンでアリアニコを使ったイタリア・カンパーニャ州の赤ワイン「タウラージ」を飲んで強く感銘を受けていた。「やるならアリアニコだ」という想いが強くなった西舘さん。 「『佐藤さん』が長野で『アリアニコ』を栽培している」というお店の情報を元に、翌日その『佐藤さん』に会いにいくことに。『佐藤さん』はよくある苗字だが、『アリアニコ』との掛け合わせで近隣のワイナリーに聞いて、辿り着いたのが佐藤果樹園の佐藤和之さん。2006年に「高山村ワインぶどう研究会」を立ち上げ、副会長としてワイン用ブドウの品質の向上、新品種の試験栽培等を担ってきた方だ。西舘さんが佐藤さんにご自分の想いを吐露したところ、佐藤さんを師として研修をスタートすることに。そして、東京に戻った西舘さんは仕事を辞め、須坂への移住を決めるのだ。 猪突猛進と言えばそうだし、そういう運命だったと言えばそうだろう。だが、可能性を見出す洞察力、即座に動く行動力、次のステップに繋げる向上心が揃っているからこそ実現したのだろう。 研修が始まる前からフルスロットル 恩師との出会い 2018年夏に辞表を提出し、須坂市に移住したのは2019年4月。移住に向けての準備で忙しいはずだが、その間も西舘さんはとにかく動く。 2018年8月に開催された「高山村ワインぶどう研究会」の研修に参加した際、角藤農園の佐藤宗一さんに出会い、意気投合。国際ワインコンクールでの受賞歴も多いカリスマ栽培家とも言われている方だ。 ▲ ヴェンティクワットロのホームページにあるnoteより。角藤農園で収穫のお手伝いをしている際の様子。 「金は払えないが飯は出す」と言われ、数週間、ブドウの収穫のお手伝いに参加することに。本格的な研修が始まる前に、収穫以外にも剪定や接ぎ木といった作業を教えてもらえたことは有難かった。そして毎晩、ワインを飲みながらワイン談義を重ねたそうだ。この経験は何にも代えられない。この話を披露して下さった西舘さんの目は下がりっぱなし。子犬がしっぽをブンブン振って母犬に向かっていくように、嬉しさが滲み出ている。 イタリアにも行く! 大きな影響を受けたワイン、タウラージが生まれる場所も見に行きたいと考えた西舘さん。2018年10月にイタリア・カンパーニャ州まで飛んだ。州都ナポリから少し内陸に入るアヴェッリーノ県では、アリアニコを使った赤ワインのタウラージのみならず、グレコやフィァーノといった白ワインも有名だ。 西舘さんは翻訳アプリを駆使しつつワイナリーやブドウ畑を見学。地元の人達が温かく迎え入れてくれ、毎晩ご飯を共にしたそう。 こういう人の温かさも含めて、アリアニコは自分にとって特別な存在 と西舘さんは言う。この思いは変わらないばかりか更に強くなり、2020年2月にも再訪したそう。 ▲...
長野・ヴェンティクワットロ
日本ワインコラム | ヴェンティクワットロ 長野県須坂市にあるブドウ畑にやってきた。2019年4月に東京から移住してきた西舘さんが管理する畑だ。 屋号はVENTIQUATTRO(ヴェンティクワットロ)。イタリア語で数字の「24」を意味する。イタリアワイン好き×「24」時間(=1日)を大切に、楽しくワインを、という想い×ご自身の苗字である西舘の西(「24」)の掛け合わせにより、この名称を選んだそう。 ▲ 取材の後日、西舘さんから頂いた畑の様子。青空と遠目に見える山々、そして畑の緑が美しい。実は、訪問日は前日から続く黄砂の影響ですっきりしない空模様且つ強風…取材中にメモ用紙が強風で吹き飛ばされ、畑中を皆で駆け回って回収するという珍プレーが…お騒がせ致しました(汗)。 西舘さんがこの地でブドウ栽培を始めるまでに、いくつもの人との出会いがある。ある出会いが次の出会いに繋がり、何かに導かれるように今、この地に立っているのだ。 動かないと始まらない 西舘さんは長い間、東京の出版業界にいた。20代の頃からワイン好きだったが、仕事とは別物として捉えてきたのだ。顧客訪問中のある時、御徒町の雑居ビルにワイナリーを発見。「こんな街中にワイナリーが⁉」と驚き、色々と話を聞く中で、これまでずっと蓋をしてきた「自分でワインを造ってみたい」という淡い夢が現実味を帯びてきた。 さて、ここからが西舘さんの凄いところ。可能性を感じたら、とにかく動く。そして自分の目で確かめる。この凄さをご理解頂くために、西舘さんの足取りを紹介したい。 ▲ 今回の取材相手の西舘さん。目じりが下がり気味の優しい笑顔をまとい、いい感じに肩の力が抜けた様子で周りの農家の方と会話をする姿が印象的。回遊魚のように動き回っているとは信じられない物腰だ。 まず、色々調べた中で話を聞いてみたいと思った新潟県のワイナリーを訪問する。そこでの研修内容は自分の希望条件と合わなかったが、先方から長野県が主催する「ワイン生産アカデミー」を受講してみてはどうかとアドバイスがあった。調べてみると受付終了の2週間前で、即座に申し込む。因みに、講座の開催場所は、現在西舘さんの畑がある須坂市だった。振り返ってみると縁を感じるセッティングだ。 受講を終え、近くのワインバーにふらっと入り、グラスワインとして提供されたイタリア品種のアリアニコを使った赤ワインにビビっと来た。実は、以前、とあるイタリアンでアリアニコを使ったイタリア・カンパーニャ州の赤ワイン「タウラージ」を飲んで強く感銘を受けていた。「やるならアリアニコだ」という想いが強くなった西舘さん。 「『佐藤さん』が長野で『アリアニコ』を栽培している」というお店の情報を元に、翌日その『佐藤さん』に会いにいくことに。『佐藤さん』はよくある苗字だが、『アリアニコ』との掛け合わせで近隣のワイナリーに聞いて、辿り着いたのが佐藤果樹園の佐藤和之さん。2006年に「高山村ワインぶどう研究会」を立ち上げ、副会長としてワイン用ブドウの品質の向上、新品種の試験栽培等を担ってきた方だ。西舘さんが佐藤さんにご自分の想いを吐露したところ、佐藤さんを師として研修をスタートすることに。そして、東京に戻った西舘さんは仕事を辞め、須坂への移住を決めるのだ。 猪突猛進と言えばそうだし、そういう運命だったと言えばそうだろう。だが、可能性を見出す洞察力、即座に動く行動力、次のステップに繋げる向上心が揃っているからこそ実現したのだろう。 研修が始まる前からフルスロットル 恩師との出会い 2018年夏に辞表を提出し、須坂市に移住したのは2019年4月。移住に向けての準備で忙しいはずだが、その間も西舘さんはとにかく動く。 2018年8月に開催された「高山村ワインぶどう研究会」の研修に参加した際、角藤農園の佐藤宗一さんに出会い、意気投合。国際ワインコンクールでの受賞歴も多いカリスマ栽培家とも言われている方だ。 ▲ ヴェンティクワットロのホームページにあるnoteより。角藤農園で収穫のお手伝いをしている際の様子。 「金は払えないが飯は出す」と言われ、数週間、ブドウの収穫のお手伝いに参加することに。本格的な研修が始まる前に、収穫以外にも剪定や接ぎ木といった作業を教えてもらえたことは有難かった。そして毎晩、ワインを飲みながらワイン談義を重ねたそうだ。この経験は何にも代えられない。この話を披露して下さった西舘さんの目は下がりっぱなし。子犬がしっぽをブンブン振って母犬に向かっていくように、嬉しさが滲み出ている。 イタリアにも行く! 大きな影響を受けたワイン、タウラージが生まれる場所も見に行きたいと考えた西舘さん。2018年10月にイタリア・カンパーニャ州まで飛んだ。州都ナポリから少し内陸に入るアヴェッリーノ県では、アリアニコを使った赤ワインのタウラージのみならず、グレコやフィァーノといった白ワインも有名だ。 西舘さんは翻訳アプリを駆使しつつワイナリーやブドウ畑を見学。地元の人達が温かく迎え入れてくれ、毎晩ご飯を共にしたそう。 こういう人の温かさも含めて、アリアニコは自分にとって特別な存在 と西舘さんは言う。この思いは変わらないばかりか更に強くなり、2020年2月にも再訪したそう。 ▲...

長野・北澤ぶどう園
日本ワインコラム | 北澤ぶどう園 「あの人、造ったワイン全部自分で飲んじゃうからな~。笑」 「北澤さんのブドウ栽培技術は本当にすごいですよ!!それに、誰に対しても分け隔てなく丁寧に教えてくれるんです。尊敬しかないです!」 今回、北澤ぶどう園にお邪魔するという話をした際、いろんな方が親しみや尊敬の眼差しを向けつつ、どちらかのセリフを口にした。同じ人のことを指しているとは思えない…が、両立してしまうのが今回の取材相手、長野県千曲市にある北澤ぶどう園の3代目、北澤文康さんの魅力だ。 ▲ 北澤ぶどう園の段々畑になっているブドウ畑の様子。 家業を継ぐつもりはなかったが性に合っていた 北澤さんが就農したのは今から約20年前。元々は家業を継ぐつもりはなく、工業高等専門学校を出て3年程別の仕事をしていたが、畑を手伝ううちに面白くなって就農したそうだ。 ▲ 「人の下で働くのは好きでないから自営が合っている」と笑う北澤さん。 北澤ぶどう園は千曲市内に位置し、長野市の善光寺と松本市を結ぶ善光寺西街道の桑原宿にある。元々は桑栽培が盛んで、その後リンゴ栽培が主流になった地域だ。そんなリンゴ全盛期の時代に、巨峰栽培を始めたのが初代。そして、2代目は周囲が巨峰ばかり育てていた30数年前に、ワイン用ブドウの栽培を始めた。 北澤家はブドウ栽培のサラブレッドであり、開拓精神に溢れたファミリーなのだ。好奇心旺盛かつ高い技術力を受け継ぐファミリーだからだろうか、現在育てている生食用ブドウの品種は30種類以上!そんな北澤さんが3代目を引き継いだのは2013年。先代の不慮の事故によるものだった。就農してから10年程経っていたとは言え、不安もあったのではないかと思うが、北澤家の開拓精神を受け継ぎ、ある挑戦に取り組んでいる。 ワイン造りだ。 なぜワイン造りなのか 自分はお酒が好きだし、せっかくワイン用ブドウを栽培しているのだから、自分で育てたブドウでワインを造ってみたかった。それに、ワインとして仕込めば保存ができ、一年中、何年後でも飲んで楽しむことができる と目を輝かせた北澤さん。お酒好きな北澤さんが、ワイン造りに目覚めるのは、時間の問題だったのだろう。しかし、理由はそれだけではなさそうだ。 ▲ 畑と近くに位置する事務所入り口。バスケットプレスや樽が外に並ぶ。 「栽培の手間がかからないワイン用ブドウ品種を開拓できれば、高齢化や耕作放棄地といった問題解決にも繋がるかもしれない。利己の心をうまく使って、他者に役立つことができれば嬉しい。」とポロリと仰る。 この感じ、いいなぁと思う。「あなたのために私は頑張ります」と言われると、言われた方はなんとなく後ろめたさを感じ、言う方もつい見返りを求めてしまうので、双方苦しくなる。だけど、北澤さんはあくまでも「自分は好きなことを楽しみながらやります」というのが先にあるので、苦しさがない。それに、本人が楽しそうだと周りにいる人も気軽に声をかけやすくなる。そうか、好循環はこうやって生まれるのかぁと気付かされるのだ。 農家目線で手繰り寄せたマルベックとの出会い 先代がワイン用ブドウを栽培し始めたのはとても早く、30数年前の1990年頃。サントリー向けの委託栽培で、ソーヴィニヨン・ブラン、シャルドネ、メルロ、ピノ・ノワールを栽培していたが、北澤さんが就農したころは、白ブドウ品種のソーヴィニヨン・ブランとシャルドネのみ畑に残っていた。 ワイン造りに興味を持つと共に、改めて赤ワイン用の黒ブドウ品種を栽培したいと考えたそうだ。 自分の好きな品種を栽培したいという気持ちはもちろんあるが、品種を選ぶ際に重視したのは、「ブドウの出来の良さ」と「差別化しやすさ」の2点だ。自分が育てる上でも大事ではあるが、この点がクリアできれば、周辺の農家が新たにワイン用ブドウ栽培を始める際のハードルがぐっと低くなると考えた。 そして、この条件を元に20品種程試験栽培を行い選んだのが…マルベックだ。 ▲ 北澤ぶどう園として販売しているワイン達。マルベックの他、シラー、ゲヴュルツトラミネール、ソーヴィニヨン・ブランなどがある。尚、写真奥の白地のラベルは、「千曲市ワインぶどう研究会」として試験醸造したマルベック。 マルベック?聞いたことがない…という方もおられるだろう。ピノ・ノワールやカベルネ・ソーヴィニヨンといった超有名品種に比べると知名度が下がるのは否めないが、侮ってはいけない魅力的な品種だ。フランス南西部カオールが原産と言われる黒ブドウで、「黒ワイン」と呼ばれるほど色調が濃いのが特徴。20世紀半ばまではボルドーでも人気を博したが、冷害で栽培量がガクンと減ることに。...
長野・北澤ぶどう園
日本ワインコラム | 北澤ぶどう園 「あの人、造ったワイン全部自分で飲んじゃうからな~。笑」 「北澤さんのブドウ栽培技術は本当にすごいですよ!!それに、誰に対しても分け隔てなく丁寧に教えてくれるんです。尊敬しかないです!」 今回、北澤ぶどう園にお邪魔するという話をした際、いろんな方が親しみや尊敬の眼差しを向けつつ、どちらかのセリフを口にした。同じ人のことを指しているとは思えない…が、両立してしまうのが今回の取材相手、長野県千曲市にある北澤ぶどう園の3代目、北澤文康さんの魅力だ。 ▲ 北澤ぶどう園の段々畑になっているブドウ畑の様子。 家業を継ぐつもりはなかったが性に合っていた 北澤さんが就農したのは今から約20年前。元々は家業を継ぐつもりはなく、工業高等専門学校を出て3年程別の仕事をしていたが、畑を手伝ううちに面白くなって就農したそうだ。 ▲ 「人の下で働くのは好きでないから自営が合っている」と笑う北澤さん。 北澤ぶどう園は千曲市内に位置し、長野市の善光寺と松本市を結ぶ善光寺西街道の桑原宿にある。元々は桑栽培が盛んで、その後リンゴ栽培が主流になった地域だ。そんなリンゴ全盛期の時代に、巨峰栽培を始めたのが初代。そして、2代目は周囲が巨峰ばかり育てていた30数年前に、ワイン用ブドウの栽培を始めた。 北澤家はブドウ栽培のサラブレッドであり、開拓精神に溢れたファミリーなのだ。好奇心旺盛かつ高い技術力を受け継ぐファミリーだからだろうか、現在育てている生食用ブドウの品種は30種類以上!そんな北澤さんが3代目を引き継いだのは2013年。先代の不慮の事故によるものだった。就農してから10年程経っていたとは言え、不安もあったのではないかと思うが、北澤家の開拓精神を受け継ぎ、ある挑戦に取り組んでいる。 ワイン造りだ。 なぜワイン造りなのか 自分はお酒が好きだし、せっかくワイン用ブドウを栽培しているのだから、自分で育てたブドウでワインを造ってみたかった。それに、ワインとして仕込めば保存ができ、一年中、何年後でも飲んで楽しむことができる と目を輝かせた北澤さん。お酒好きな北澤さんが、ワイン造りに目覚めるのは、時間の問題だったのだろう。しかし、理由はそれだけではなさそうだ。 ▲ 畑と近くに位置する事務所入り口。バスケットプレスや樽が外に並ぶ。 「栽培の手間がかからないワイン用ブドウ品種を開拓できれば、高齢化や耕作放棄地といった問題解決にも繋がるかもしれない。利己の心をうまく使って、他者に役立つことができれば嬉しい。」とポロリと仰る。 この感じ、いいなぁと思う。「あなたのために私は頑張ります」と言われると、言われた方はなんとなく後ろめたさを感じ、言う方もつい見返りを求めてしまうので、双方苦しくなる。だけど、北澤さんはあくまでも「自分は好きなことを楽しみながらやります」というのが先にあるので、苦しさがない。それに、本人が楽しそうだと周りにいる人も気軽に声をかけやすくなる。そうか、好循環はこうやって生まれるのかぁと気付かされるのだ。 農家目線で手繰り寄せたマルベックとの出会い 先代がワイン用ブドウを栽培し始めたのはとても早く、30数年前の1990年頃。サントリー向けの委託栽培で、ソーヴィニヨン・ブラン、シャルドネ、メルロ、ピノ・ノワールを栽培していたが、北澤さんが就農したころは、白ブドウ品種のソーヴィニヨン・ブランとシャルドネのみ畑に残っていた。 ワイン造りに興味を持つと共に、改めて赤ワイン用の黒ブドウ品種を栽培したいと考えたそうだ。 自分の好きな品種を栽培したいという気持ちはもちろんあるが、品種を選ぶ際に重視したのは、「ブドウの出来の良さ」と「差別化しやすさ」の2点だ。自分が育てる上でも大事ではあるが、この点がクリアできれば、周辺の農家が新たにワイン用ブドウ栽培を始める際のハードルがぐっと低くなると考えた。 そして、この条件を元に20品種程試験栽培を行い選んだのが…マルベックだ。 ▲ 北澤ぶどう園として販売しているワイン達。マルベックの他、シラー、ゲヴュルツトラミネール、ソーヴィニヨン・ブランなどがある。尚、写真奥の白地のラベルは、「千曲市ワインぶどう研究会」として試験醸造したマルベック。 マルベック?聞いたことがない…という方もおられるだろう。ピノ・ノワールやカベルネ・ソーヴィニヨンといった超有名品種に比べると知名度が下がるのは否めないが、侮ってはいけない魅力的な品種だ。フランス南西部カオールが原産と言われる黒ブドウで、「黒ワイン」と呼ばれるほど色調が濃いのが特徴。20世紀半ばまではボルドーでも人気を博したが、冷害で栽培量がガクンと減ることに。...

北海道・余市 ドメーヌタカヒコ
日本ワインコラム 北海道・余市 ドメーヌタカヒコ / vol.3 ----- 訪問日:2023年9月6日 / vol.1 はこちら/ vol.2 はこちら 3度目となる曽我さんへの取材。 11月23日に申し込み開始となる北海道余市町へのふるさと納税の返礼品として用意された「ドメーヌ・タカヒコ ヨイチ・ノボリ ニ 2022」についてのアレコレをお伺いすることを目的に訪問した。 ふるさと納税の返礼品を手掛けることになったきっかけとは? 2022年3月、オーストリアに本社がある老舗ワイングラスメーカーの「リーデル・ジャパン」と余市町は、ワイン産地としての余市の魅力を広く伝えるべく、包括連携協定を結んでいる。この協定をベースに、同年8月に東京リーデル銀座店の一角で余市ワインに関するイベントが行われたので、読者の中には、イベント参加を通じてご存知の方もおられるかもしれない。 ▲ リーデル銀座店で設けられた余市ワインツーリズムポップアップコーナーの様子。リーデル・ジャパンのホームページより。 協定を通じた連携はイベント開催に留まらない。今回の余市町へのふるさと納税返礼品プロジェクトもその一つだ。そこで白羽の矢が立ったのが、そう、ドメーヌ・タカヒコ。リーデル・ジャパンと余市町町長の双方から熱烈なラブコールがあり、受けたそうだ。 消費者としては、「お~❤」である。国内のみならず、世界的にも有名なワイナリーであるドメーヌ・タカヒコ。どの商品もあっという間に完売してしまう、日本で最も入手困難といっても過言ではないワインを試せるチャンスだ。しかも、ふるさと納税を通じて、ワインを軸にまちづくりを進めようとする余市町の取り組みの後押しができるのだから、ワインラバーとしては「喜んで!」の一言に尽きる。 ▲ ワインが眠る樽が積み上げられている姿はとても美しい! 返礼品の内容とは? 気になる返礼品の中身を聞いてみた。なんと、「返礼品用にワインを特別に仕込んだ」と曽我さんは仰るではないか。その名は「ドメーヌ・タカヒコ ヨイチ・ノボリ 二 2022」。商品名にある「ニ」に、今回のワインの秘密が隠されているそうだ。...
北海道・余市 ドメーヌタカヒコ
日本ワインコラム 北海道・余市 ドメーヌタカヒコ / vol.3 ----- 訪問日:2023年9月6日 / vol.1 はこちら/ vol.2 はこちら 3度目となる曽我さんへの取材。 11月23日に申し込み開始となる北海道余市町へのふるさと納税の返礼品として用意された「ドメーヌ・タカヒコ ヨイチ・ノボリ ニ 2022」についてのアレコレをお伺いすることを目的に訪問した。 ふるさと納税の返礼品を手掛けることになったきっかけとは? 2022年3月、オーストリアに本社がある老舗ワイングラスメーカーの「リーデル・ジャパン」と余市町は、ワイン産地としての余市の魅力を広く伝えるべく、包括連携協定を結んでいる。この協定をベースに、同年8月に東京リーデル銀座店の一角で余市ワインに関するイベントが行われたので、読者の中には、イベント参加を通じてご存知の方もおられるかもしれない。 ▲ リーデル銀座店で設けられた余市ワインツーリズムポップアップコーナーの様子。リーデル・ジャパンのホームページより。 協定を通じた連携はイベント開催に留まらない。今回の余市町へのふるさと納税返礼品プロジェクトもその一つだ。そこで白羽の矢が立ったのが、そう、ドメーヌ・タカヒコ。リーデル・ジャパンと余市町町長の双方から熱烈なラブコールがあり、受けたそうだ。 消費者としては、「お~❤」である。国内のみならず、世界的にも有名なワイナリーであるドメーヌ・タカヒコ。どの商品もあっという間に完売してしまう、日本で最も入手困難といっても過言ではないワインを試せるチャンスだ。しかも、ふるさと納税を通じて、ワインを軸にまちづくりを進めようとする余市町の取り組みの後押しができるのだから、ワインラバーとしては「喜んで!」の一言に尽きる。 ▲ ワインが眠る樽が積み上げられている姿はとても美しい! 返礼品の内容とは? 気になる返礼品の中身を聞いてみた。なんと、「返礼品用にワインを特別に仕込んだ」と曽我さんは仰るではないか。その名は「ドメーヌ・タカヒコ ヨイチ・ノボリ 二 2022」。商品名にある「ニ」に、今回のワインの秘密が隠されているそうだ。...

北海道・ 余市 豊丘西尾ヴィンヤード
日本ワインコラム | 北海道・余市 豊丘西尾ヴィンヤード 2021年1月に余市町に農地を取得し新規就農された、豊丘西尾ヴィンヤードの西尾さんに会いにやってきた。Google Mapで場所を検索し目指したのだが、最後に曲がる場所を何度も間違い、右往左往。西尾さんに電話して、なんとか辿り着くことができた(我々が勝手に迷っただけで、そんなに難しい場所ではないので、ご安心を!)。優しい微笑みで迎え入れて下さった西尾さん。我々が迷っている様子を遠目にご覧になっていたそうで、お恥ずかしい限りだ… ▲ 無事に到着して一安心! ワインにハマる 埼玉県ご出身の西尾さん。大学卒業後大手製薬会社に入社、全国各地にある支店で30年近く営業として勤務されてきた。そんな中、25年前に在籍した名古屋支店でワインに目覚めたそう。色んなタイプのワインを飲むようになると共に、ワイン本も読み始める。日本語になっているワイン本はほぼ読破したとのこと!今も読むのはワインの本ばかり。ワインが好きになったからといって、仕事をしつつ、ここまで貪欲に知識を身に付ける人はそうはいないだろう。沼にはまるとは、正にこのことだ。 ▲ 畑の一角にある木陰に陣取り、収穫籠を裏返した椅子に座ってお話を聞いた。風を感じて気持ちいい。 本を読めば読むほど、気付いたことがある。ワイン造りとは、即ちブドウ栽培であると。よいブドウを育てられれば、醸造の過程でテクニックを駆使する必要はない。自分もいいブドウを育てたい。そして、自分が思い描くワインを造りたい…。サラリーマンをしながら、抑えられない気持ちが溢れてきた。 マラソンとの出会い~50歳でもまだまだイケル~ ワインに並行して、サラリーマン時代に出会ったものがある。マラソンだ。40歳頃、本格的にゴルフに打ち込もうと思い、足腰を鍛えるためにマラソンを始めたら、マラソンにハマってしまったそうだ。好きになったらとことん突き詰める西尾さん。北海道のフルマラソンは10回以上、サロマ湖の100キロウルトラマラソンは2回完走したそうだ(う、嘘でしょ… )!しかも100キロマラソンは13時間以内に走り切ることが求められるそうで、西尾さんは12時間ちょっとで完走。100キロマラソンって、サライの音楽を聴きながら感動のフィナーレを迎える24時間テレビの中でしか聞いたことがない。24時間の半分の時間で完走してしまうなんて…超人サラリーマンだ。趣味の域を越えていませんか? ▲ 第38回サロマ湖100kmウルトラマラソン公式サイトより。湖の周りなので景色は良さそうだが、車でのんびり周りたい距離だ… 「100キロマラソンをやると、体力的にこれを上回ることって世の中にないと思えるんです」 そりゃそうでしょう…レベルが違う話に圧倒されてしまう。超人だからこそできることなのかもしれないが、この経験が西尾さんにとっての転機となる。 「今考えると、小さいころから生き物を育てたりするのが好きで、自分で何かを作る農家になりたいという夢はあった。また、マラソンに関しては、膝を悪くするし、辛いだけだし、変わった人がするものだと思っていた」と笑った西尾さん。しかし100キロマラソンを完走すると、「そうでもないぞ」と気付いてしまったのだ。また、マラソンを始めてから良質のたんぱく源を摂取しようと考え、苦手だった納豆が食べられるようにもなった。嫌いだと思い込んでいたものも、意外にそうではない。 「歳をとっても、意外と何でもできるじゃん」 そう気付いたのだ。 ▲ 手作りのポストが可愛らしい。マラソンを始めるまで、ブドウ栽培をしているご自身を想像していなかったに違いない。 「ワインの道に進みたい」と家族に切り出したのは、娘さんが小学校4年生の時。子育て真っただ中だったこともあり、そのタイミングでの就農は諦めたそうだが、将来に向けて週末を就農に向けた準備に使うことにOKは出た。寛大な奥様である。そして、娘さんが大学生になったタイミング、西尾さんが50歳を過ぎてからの就農となるのだ。 準備してきたからこそ適った就農 西尾さんが会社を辞めたのは2020年12月、そして現在の畑を取得し就農したのは翌月の2021年1月。しかも就農3年目となる2023年5月には、ご自身が育てたブドウでワインの発売までやってのけている。一般的に、就農からワイン発売まで5年はかかると言われている中、すごいスピード感だ。 ▲ 上空から見た畑の様子。取材時は曇り空だったが、南南西向きの畑は陽当たりがよい。...
北海道・ 余市 豊丘西尾ヴィンヤード
日本ワインコラム | 北海道・余市 豊丘西尾ヴィンヤード 2021年1月に余市町に農地を取得し新規就農された、豊丘西尾ヴィンヤードの西尾さんに会いにやってきた。Google Mapで場所を検索し目指したのだが、最後に曲がる場所を何度も間違い、右往左往。西尾さんに電話して、なんとか辿り着くことができた(我々が勝手に迷っただけで、そんなに難しい場所ではないので、ご安心を!)。優しい微笑みで迎え入れて下さった西尾さん。我々が迷っている様子を遠目にご覧になっていたそうで、お恥ずかしい限りだ… ▲ 無事に到着して一安心! ワインにハマる 埼玉県ご出身の西尾さん。大学卒業後大手製薬会社に入社、全国各地にある支店で30年近く営業として勤務されてきた。そんな中、25年前に在籍した名古屋支店でワインに目覚めたそう。色んなタイプのワインを飲むようになると共に、ワイン本も読み始める。日本語になっているワイン本はほぼ読破したとのこと!今も読むのはワインの本ばかり。ワインが好きになったからといって、仕事をしつつ、ここまで貪欲に知識を身に付ける人はそうはいないだろう。沼にはまるとは、正にこのことだ。 ▲ 畑の一角にある木陰に陣取り、収穫籠を裏返した椅子に座ってお話を聞いた。風を感じて気持ちいい。 本を読めば読むほど、気付いたことがある。ワイン造りとは、即ちブドウ栽培であると。よいブドウを育てられれば、醸造の過程でテクニックを駆使する必要はない。自分もいいブドウを育てたい。そして、自分が思い描くワインを造りたい…。サラリーマンをしながら、抑えられない気持ちが溢れてきた。 マラソンとの出会い~50歳でもまだまだイケル~ ワインに並行して、サラリーマン時代に出会ったものがある。マラソンだ。40歳頃、本格的にゴルフに打ち込もうと思い、足腰を鍛えるためにマラソンを始めたら、マラソンにハマってしまったそうだ。好きになったらとことん突き詰める西尾さん。北海道のフルマラソンは10回以上、サロマ湖の100キロウルトラマラソンは2回完走したそうだ(う、嘘でしょ… )!しかも100キロマラソンは13時間以内に走り切ることが求められるそうで、西尾さんは12時間ちょっとで完走。100キロマラソンって、サライの音楽を聴きながら感動のフィナーレを迎える24時間テレビの中でしか聞いたことがない。24時間の半分の時間で完走してしまうなんて…超人サラリーマンだ。趣味の域を越えていませんか? ▲ 第38回サロマ湖100kmウルトラマラソン公式サイトより。湖の周りなので景色は良さそうだが、車でのんびり周りたい距離だ… 「100キロマラソンをやると、体力的にこれを上回ることって世の中にないと思えるんです」 そりゃそうでしょう…レベルが違う話に圧倒されてしまう。超人だからこそできることなのかもしれないが、この経験が西尾さんにとっての転機となる。 「今考えると、小さいころから生き物を育てたりするのが好きで、自分で何かを作る農家になりたいという夢はあった。また、マラソンに関しては、膝を悪くするし、辛いだけだし、変わった人がするものだと思っていた」と笑った西尾さん。しかし100キロマラソンを完走すると、「そうでもないぞ」と気付いてしまったのだ。また、マラソンを始めてから良質のたんぱく源を摂取しようと考え、苦手だった納豆が食べられるようにもなった。嫌いだと思い込んでいたものも、意外にそうではない。 「歳をとっても、意外と何でもできるじゃん」 そう気付いたのだ。 ▲ 手作りのポストが可愛らしい。マラソンを始めるまで、ブドウ栽培をしているご自身を想像していなかったに違いない。 「ワインの道に進みたい」と家族に切り出したのは、娘さんが小学校4年生の時。子育て真っただ中だったこともあり、そのタイミングでの就農は諦めたそうだが、将来に向けて週末を就農に向けた準備に使うことにOKは出た。寛大な奥様である。そして、娘さんが大学生になったタイミング、西尾さんが50歳を過ぎてからの就農となるのだ。 準備してきたからこそ適った就農 西尾さんが会社を辞めたのは2020年12月、そして現在の畑を取得し就農したのは翌月の2021年1月。しかも就農3年目となる2023年5月には、ご自身が育てたブドウでワインの発売までやってのけている。一般的に、就農からワイン発売まで5年はかかると言われている中、すごいスピード感だ。 ▲ 上空から見た畑の様子。取材時は曇り空だったが、南南西向きの畑は陽当たりがよい。...

北海道・ ロウブロウ・クラフト
日本ワインコラム | 北海道・余市 ロウブロウ・クラフト 2022年10月にワイン醸造を始めたLowbrow Craft(ロウブロウ・クラフト)。北海道余市町で16軒目となる新しいワイナリーだ。通常、取材前に可能な限り情報収集するのだが、新しいワイナリーということもあり、ワイナリーの情報も取材相手の赤城さんの情報も限られていた。 その中で目を引いたのが、ワインのラベルと赤城さんの風貌。ワインラベルはロックな感じもするし、インダストリアルな感じもある。どことなくストリート・アートといった雰囲気がある。赤城さんは、長い髭と雑誌のストリート・スナップで選ばれそうなセンスの良さが印象的で、アーティストか?はたまたヨガ・インストラクターか?と思ってしまう(勝手な印象です)。どんな方がどんなワインを造っているのだろう?想像が膨らむ先である。 ▲ Lowbrow CraftのFacebookアカウントより。左のプロフィール写真には、思わずクスっと笑ってしまう。右3つのワインボトルは、一見するとワインのエチケットとは思えない仕上がりで、じっと見入ってしまう。 セレンディピティを楽しむ 今回取材した赤城さんは千葉県ご出身。2014年にご夫婦で北海道・余市町に移住された。やはりワイン造りを目指して、移住されたのだろうか? 「最初からワイナリーをするつもりで移住したわけではないんですよ。①北海道に住みたい、②農業がやりたい、③酒が好き、という3つの条件で探していたら、北海道でワインを造る会社があったので、夫婦でそこに就職した、というのがきっかけです。」 ▲ 立派なお鬚をたくわえ、ファッション雑誌の特集で取り上げられそうな程オシャレな赤城さん。優しい笑顔の持ち主だ。 移住した時は、何が何でもワインに携わりたいというわけではなく、むしろビールが一番好きだったというのだから面白い。因みにキリンやサッポロが好きらしい。「念願の北海道だし、ブドウ栽培農家になれるし、ワインもビールと同じお酒だし、面白そうじゃないか」という気持ちで移住されたそう。「こうじゃなければいけない」という拘りがなく、何事も面白がれる柔軟さがある。赤城さんと話していると、何かをコントロールしようという気持ちが皆無なことに気付く。たまたま起こるセレンディピティ(素敵な偶然)を気負いなく楽しんでしまう人なのだ。 自分でやってみたい その企業で4年間ブドウ栽培を続けていく中で、ワイン醸造にも関心を持つようになる。しかし、組織の一部である以上、ワイン造りの全ての工程を担当することは難しかった。また、企業には企業の論理があると理解しつつも、慣行農法を用い、量産を狙う手法に疑問を覚えるようにもなった。 「自分の考える方法で、ワイン造りの最初から最後まで一貫してやりたい」 「自分が造ったもので評価されたい」 ブドウ栽培を続けるなかで、この気持ちがじわじわと強くなっていく。 ▲ くぅぅっという声が聞こえてきそうな表情もたまらない。笑 ▲ 赤城さんが3年間修行したドメーヌ・タカヒコ。 ドメーヌ・タカヒコの曽我氏との出会いも大きい。有機栽培されたブドウを用い、野生酵母で醸造された彼のワインの美味しさに感銘を受けた。また、彼が提唱する、農家による小規模なワイナリーというアイディアに心が惹かれた。ガレージ・ワイナリーのようでカッコいいし、頑張れば自分でもできるのではないか、という気持ちが湧いたと言う。ワイナリー経営が現実的になり、独立を決意する。 偶然を面白がり、フィルターのない気持ちで目の前の仕事に取り組むからこそ、次のステップが開けるのだろう。移住時には想像もしていなかったことに違いない。 山の力を感じる畑との出会い ガレージ・ワイナリーという新しい目標ができた赤城さん。退職後の2019年に今の畑と出会う。元々リンゴが植わっていたそうだが、何年も耕作放棄されていたため、開墾は想像以上に重労働。しかも驚きなのが、同時期の2019年から3年間、ドメーヌ・タカヒコで研修を受けていたことだ。ドメーヌ・タカヒコでみっちり研修を受けつつ、同時並行して自分の畑の開墾やブドウ栽培を行ってきたというのだから、人の数倍働いていたに違いない。信じられない体力と精神力の持ち主だ。 ▲ まさに山の中に畑があるといった雰囲気の場所だ!...
北海道・ ロウブロウ・クラフト
日本ワインコラム | 北海道・余市 ロウブロウ・クラフト 2022年10月にワイン醸造を始めたLowbrow Craft(ロウブロウ・クラフト)。北海道余市町で16軒目となる新しいワイナリーだ。通常、取材前に可能な限り情報収集するのだが、新しいワイナリーということもあり、ワイナリーの情報も取材相手の赤城さんの情報も限られていた。 その中で目を引いたのが、ワインのラベルと赤城さんの風貌。ワインラベルはロックな感じもするし、インダストリアルな感じもある。どことなくストリート・アートといった雰囲気がある。赤城さんは、長い髭と雑誌のストリート・スナップで選ばれそうなセンスの良さが印象的で、アーティストか?はたまたヨガ・インストラクターか?と思ってしまう(勝手な印象です)。どんな方がどんなワインを造っているのだろう?想像が膨らむ先である。 ▲ Lowbrow CraftのFacebookアカウントより。左のプロフィール写真には、思わずクスっと笑ってしまう。右3つのワインボトルは、一見するとワインのエチケットとは思えない仕上がりで、じっと見入ってしまう。 セレンディピティを楽しむ 今回取材した赤城さんは千葉県ご出身。2014年にご夫婦で北海道・余市町に移住された。やはりワイン造りを目指して、移住されたのだろうか? 「最初からワイナリーをするつもりで移住したわけではないんですよ。①北海道に住みたい、②農業がやりたい、③酒が好き、という3つの条件で探していたら、北海道でワインを造る会社があったので、夫婦でそこに就職した、というのがきっかけです。」 ▲ 立派なお鬚をたくわえ、ファッション雑誌の特集で取り上げられそうな程オシャレな赤城さん。優しい笑顔の持ち主だ。 移住した時は、何が何でもワインに携わりたいというわけではなく、むしろビールが一番好きだったというのだから面白い。因みにキリンやサッポロが好きらしい。「念願の北海道だし、ブドウ栽培農家になれるし、ワインもビールと同じお酒だし、面白そうじゃないか」という気持ちで移住されたそう。「こうじゃなければいけない」という拘りがなく、何事も面白がれる柔軟さがある。赤城さんと話していると、何かをコントロールしようという気持ちが皆無なことに気付く。たまたま起こるセレンディピティ(素敵な偶然)を気負いなく楽しんでしまう人なのだ。 自分でやってみたい その企業で4年間ブドウ栽培を続けていく中で、ワイン醸造にも関心を持つようになる。しかし、組織の一部である以上、ワイン造りの全ての工程を担当することは難しかった。また、企業には企業の論理があると理解しつつも、慣行農法を用い、量産を狙う手法に疑問を覚えるようにもなった。 「自分の考える方法で、ワイン造りの最初から最後まで一貫してやりたい」 「自分が造ったもので評価されたい」 ブドウ栽培を続けるなかで、この気持ちがじわじわと強くなっていく。 ▲ くぅぅっという声が聞こえてきそうな表情もたまらない。笑 ▲ 赤城さんが3年間修行したドメーヌ・タカヒコ。 ドメーヌ・タカヒコの曽我氏との出会いも大きい。有機栽培されたブドウを用い、野生酵母で醸造された彼のワインの美味しさに感銘を受けた。また、彼が提唱する、農家による小規模なワイナリーというアイディアに心が惹かれた。ガレージ・ワイナリーのようでカッコいいし、頑張れば自分でもできるのではないか、という気持ちが湧いたと言う。ワイナリー経営が現実的になり、独立を決意する。 偶然を面白がり、フィルターのない気持ちで目の前の仕事に取り組むからこそ、次のステップが開けるのだろう。移住時には想像もしていなかったことに違いない。 山の力を感じる畑との出会い ガレージ・ワイナリーという新しい目標ができた赤城さん。退職後の2019年に今の畑と出会う。元々リンゴが植わっていたそうだが、何年も耕作放棄されていたため、開墾は想像以上に重労働。しかも驚きなのが、同時期の2019年から3年間、ドメーヌ・タカヒコで研修を受けていたことだ。ドメーヌ・タカヒコでみっちり研修を受けつつ、同時並行して自分の畑の開墾やブドウ栽培を行ってきたというのだから、人の数倍働いていたに違いない。信じられない体力と精神力の持ち主だ。 ▲ まさに山の中に畑があるといった雰囲気の場所だ!...
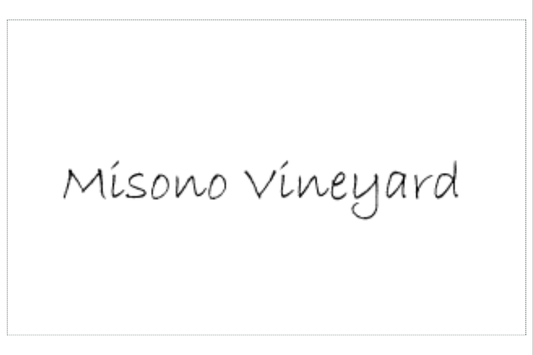
北海道・余市 Misono Vineyard
日本ワインコラム | 北海道・余市 Misono Vineyard 「好きこそ物の上手なれ」 そうは言われても、好きを生業にするのは難しい。好きなことを仕事にしたいと思っていても、なかなかその一歩を踏み出せない。食べていけるのか?という現実的な問題が立ちはだかり、自分の気持ちと生活の糧を天秤にかけて、自分の気持ちにそっと蓋をする。大半の人間はそうだろう。 今回取材をしたMisono Vineyardの松村さんは違う。大手総合商社で航空機関連やTV放送業務など、世界を股にかけてバリバリ仕事をしていたにも関わらず、「ブルゴーニュワインが好き」という一点で、誰もが羨む仕事を手放し、東京・青山でブルゴーニュとシャンパーニュ専門のワインバーの経営に乗り出す。しかし、ワインを提供するだけでは飽き足らず、今度は自分でワインを造るという道を進み出したのだ。 ▲ ワイナリーの入り口には、青山で経営していたワインバー「Burgundy」の看板が飾ってある。 かくして、2019年に北海道余市町で元牧草地を購入、翌年2020年には隣接する元果樹園を購入する。そして、2021年にはワイン製造免許を取得し、Misono Vineyardが誕生するのだ。「好き」のレベルが違うのか、心の声に忠実なのか…驚くべき行動力だ。「好き」が原動力だからこそ、自分の好きなブルゴーニュワインが教科書でありバイブル。そして研究は徹底的に行い、自分の選択に対するロジックはシンプルで明快。話を聞いていると、魔法をかけられたかのように松村さんと同じ思考になっていくのだ。笑 ▲ 写真中央の柏(ドングリ)の大木と小道を挟んで右側が元牧草地、左側が元果樹園の畑。東向きの丘陵地で陽当たりも風通しも抜群の立地だ。 ブルゴーニュ地方のコート・ドールを思わせる畑との出会い 2018年、青山でワインバーを経営しながら、長野県にある千曲川ワインアカデミーで、ブドウ栽培とワイン醸造、ワイナリー経営などを学ぶと共に、自身のワイナリー設営に向けた畑も探していた。長野県内でも畑を探したが、土地が細分化されていて、纏まった土地を入手するには多数の地主の了解を得る必要があり、現実的ではなかった。 そんな中、余市で出会った現在の畑は魅力的だった。元牧草地と元果樹園はそれぞれ4haと広大で、地主もそれぞれ1人だけ。 東向きの丘陵地はブルゴーニュ地方のコート・ドールの丘を彷彿とさせ、ブルゴーニュ好きの心がくすぐられた。朝日を浴び、風も抜けるので湿気が溜まらない環境。日本海と余市川を臨む位置にあり、海や川に近く温暖な環境なのも素晴らしい。特に気に入ったのはサクランボや梨などが植えられていた元果樹園だ。温暖な気候を活かした早生のサクランボ(佐藤錦)が人気で、有名芸能人がお取り寄せしていたそう。元果樹園の土地を狙っていたが、先に決まったのは隣の元牧草地。少し肩透かしをくらったが、翌年には狙っていた元果樹園も手に入るのだから、万々歳としか言いようがない。 ▲ 丘になっている頂上付近からは、余市の街並みと海が見渡せる。あぁ絶景かな。 畑を開墾して嬉しい発見もした。土壌が灰色火山礫が風化してできた白灰色の細かい土で、水はけに優れているのだ。余市では保水性に富む赤粘土土壌のところが多い中、世界の銘醸地に比べ降雨量が多い日本の環境を考慮すると、水はけの良い土壌を確保できるのは非常に有難い。温暖な気候、風通しの良さ、水はけの良さ。必要だと考えていた要素が揃う場所に巡り合えた。 ▲ ゴロゴロとした灰色火山礫の石ころや、それが風化してできた細かい土。余市ではなかなか出会えない土壌だ。 ブルゴーニュに想いを馳せた品種選び やっぱりブルゴーニュワインが好きだから 栽培品種で一番栽培面積が広いのはもちろん、ブルゴーニュワインの筆頭品種であるピノ・ノワール(2ha)とシャルドネ(1ha)。計8haの畑の植栽面積が6haなので、全体の半分を占める。 ▲ 圃場の植栽品種マップ。初公開となる超貴重な一枚だ!掲載OK、ありがとうございます!! 特に元果樹園に植わるシャルドネの出来は最高だそうだ。基本的に畑は東向きの斜面だが、シャルドネが植わっている一角のみ南東向きの斜面になっており、畑の中でも特に温暖な環境。人気の早生のサクランボもこの場所で栽培されていたらしい。また、実際に栽培してみて、余市の環境はピノ・ノワールの栽培に向いていると実感。余市では、昔からツヴァイゲルトレーベとケルナーが盛んに栽培されてきており、今も栽培面積は広い。ただ、昨今の温暖化の影響で酸落ちしやすいのも事実だそう。そんな中、栽培が難しいと言われてきたピノ・ノワールは逆に、温暖化の影響で栽培しやすい品種になってきた。Misono Vineyardでも一番出来がいいと感じているそうだ。...
北海道・余市 Misono Vineyard
日本ワインコラム | 北海道・余市 Misono Vineyard 「好きこそ物の上手なれ」 そうは言われても、好きを生業にするのは難しい。好きなことを仕事にしたいと思っていても、なかなかその一歩を踏み出せない。食べていけるのか?という現実的な問題が立ちはだかり、自分の気持ちと生活の糧を天秤にかけて、自分の気持ちにそっと蓋をする。大半の人間はそうだろう。 今回取材をしたMisono Vineyardの松村さんは違う。大手総合商社で航空機関連やTV放送業務など、世界を股にかけてバリバリ仕事をしていたにも関わらず、「ブルゴーニュワインが好き」という一点で、誰もが羨む仕事を手放し、東京・青山でブルゴーニュとシャンパーニュ専門のワインバーの経営に乗り出す。しかし、ワインを提供するだけでは飽き足らず、今度は自分でワインを造るという道を進み出したのだ。 ▲ ワイナリーの入り口には、青山で経営していたワインバー「Burgundy」の看板が飾ってある。 かくして、2019年に北海道余市町で元牧草地を購入、翌年2020年には隣接する元果樹園を購入する。そして、2021年にはワイン製造免許を取得し、Misono Vineyardが誕生するのだ。「好き」のレベルが違うのか、心の声に忠実なのか…驚くべき行動力だ。「好き」が原動力だからこそ、自分の好きなブルゴーニュワインが教科書でありバイブル。そして研究は徹底的に行い、自分の選択に対するロジックはシンプルで明快。話を聞いていると、魔法をかけられたかのように松村さんと同じ思考になっていくのだ。笑 ▲ 写真中央の柏(ドングリ)の大木と小道を挟んで右側が元牧草地、左側が元果樹園の畑。東向きの丘陵地で陽当たりも風通しも抜群の立地だ。 ブルゴーニュ地方のコート・ドールを思わせる畑との出会い 2018年、青山でワインバーを経営しながら、長野県にある千曲川ワインアカデミーで、ブドウ栽培とワイン醸造、ワイナリー経営などを学ぶと共に、自身のワイナリー設営に向けた畑も探していた。長野県内でも畑を探したが、土地が細分化されていて、纏まった土地を入手するには多数の地主の了解を得る必要があり、現実的ではなかった。 そんな中、余市で出会った現在の畑は魅力的だった。元牧草地と元果樹園はそれぞれ4haと広大で、地主もそれぞれ1人だけ。 東向きの丘陵地はブルゴーニュ地方のコート・ドールの丘を彷彿とさせ、ブルゴーニュ好きの心がくすぐられた。朝日を浴び、風も抜けるので湿気が溜まらない環境。日本海と余市川を臨む位置にあり、海や川に近く温暖な環境なのも素晴らしい。特に気に入ったのはサクランボや梨などが植えられていた元果樹園だ。温暖な気候を活かした早生のサクランボ(佐藤錦)が人気で、有名芸能人がお取り寄せしていたそう。元果樹園の土地を狙っていたが、先に決まったのは隣の元牧草地。少し肩透かしをくらったが、翌年には狙っていた元果樹園も手に入るのだから、万々歳としか言いようがない。 ▲ 丘になっている頂上付近からは、余市の街並みと海が見渡せる。あぁ絶景かな。 畑を開墾して嬉しい発見もした。土壌が灰色火山礫が風化してできた白灰色の細かい土で、水はけに優れているのだ。余市では保水性に富む赤粘土土壌のところが多い中、世界の銘醸地に比べ降雨量が多い日本の環境を考慮すると、水はけの良い土壌を確保できるのは非常に有難い。温暖な気候、風通しの良さ、水はけの良さ。必要だと考えていた要素が揃う場所に巡り合えた。 ▲ ゴロゴロとした灰色火山礫の石ころや、それが風化してできた細かい土。余市ではなかなか出会えない土壌だ。 ブルゴーニュに想いを馳せた品種選び やっぱりブルゴーニュワインが好きだから 栽培品種で一番栽培面積が広いのはもちろん、ブルゴーニュワインの筆頭品種であるピノ・ノワール(2ha)とシャルドネ(1ha)。計8haの畑の植栽面積が6haなので、全体の半分を占める。 ▲ 圃場の植栽品種マップ。初公開となる超貴重な一枚だ!掲載OK、ありがとうございます!! 特に元果樹園に植わるシャルドネの出来は最高だそうだ。基本的に畑は東向きの斜面だが、シャルドネが植わっている一角のみ南東向きの斜面になっており、畑の中でも特に温暖な環境。人気の早生のサクランボもこの場所で栽培されていたらしい。また、実際に栽培してみて、余市の環境はピノ・ノワールの栽培に向いていると実感。余市では、昔からツヴァイゲルトレーベとケルナーが盛んに栽培されてきており、今も栽培面積は広い。ただ、昨今の温暖化の影響で酸落ちしやすいのも事実だそう。そんな中、栽培が難しいと言われてきたピノ・ノワールは逆に、温暖化の影響で栽培しやすい品種になってきた。Misono Vineyardでも一番出来がいいと感じているそうだ。...