日本ワインコラム
THE CELLAR ワイン特集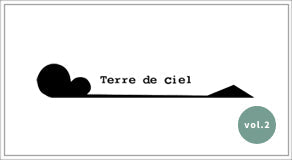
日本ワインコラム | 長野・テール・ド・シエル vol.2
日本ワインコラム | 長野 テール・ド・シエル vol.2 / vol.1 はこちら 約3年ぶり、2度目の来訪となった。 奥行きのあるパノラマの景色、優しく吹き抜ける風、ふかふかの土…何度も立ち止まって深呼吸したくなる場所だ。前回訪問時に味わった感動は全く色褪せることなく、むしろより色濃くなって溢れ出す。何度来ても、「気持ちいい…」という言葉が口に出る、心地の良い空間に佇むのが、テール・ド・シエルの畑と醸造所だ。 ▲ やはりこの場所は何度来ても癒される。じわぁっと体がほぐれていくのだ。 ブドウ栽培、ワイン醸造への真摯な姿勢はそのままに(テール・ド・シエルの成り立ちやワイン造りの考え方についてはVol.1へ)。その上で、3年という月日を経て得た新たな気付きについて、栽培と醸造の責任者を務める桒原さんに色々伺った。 ▲ 前回と変わらない桒原さんの出で立ちに嬉しくなる! 畑は広がっても、きめ細やかな管理を徹底する 元々雑木林だったところを2015年に開墾し始め、10年が経過した。畑は4haまで広がったが、来年は更に60-70a広げ、5ha弱となる見込みだ。開墾する際に気を付けたのは、山を削ることなく、元々の地形をそのまま残すこと。その結果、テール・ド・シエルの畑は色んな方向を向いた様々な角度の斜面となっている。美しい景色が広がるが、急な斜面が多いため機械化は難しく、手作業中心とならざるを得ないし、一枚畑に比べると畑の管理に時間を要するので、栽培者にかかる負荷は大きい。 ▲ 畑の土壌は、7-8割程度を占める粘土質に2-3割程度の火山灰が混ざったもの。千曲川左岸の強粘土質の土壌に比べると、粘土の割合は少ない。 お邪魔した際、1回目の芽かき作業が終わり、誘引を行っているところだった。広い畑なので、1回の芽かきで2-3週間要するという。今年はミノムシが大量発生したそう。ブドウの新芽や葉を食害するのでやっかいな存在だ。これまでに500匹捕殺したとのことだが(驚愕!)、ブドウの収量に影響が出ないよう、1度目の芽かきは慎重に行い、2度目で収量調整を行う予定だという。自然相手の畑で、殺虫剤の使用も極限まで減らしているからこそ、細かい畑の観察とこまめな対策が不可欠なのだ。また、畑では除草剤も使用しないので、草刈りも一仕事。一巡したと思ったら、最初の畑の草は伸びているとのこと。骨の折れる作業を地道に繰り返されているのだ。 ▲ キレイに並ぶブドウの樹。根元も含め、草刈りがしっかりと行われているのがよく分かる。 ▲ 誘引作業により、2本のワイヤーの間に枝がきちんと収まっている。 流石にこの広さを一人で管理しきれないので、地元のシルバーさんに助けてもらっているとのこと。「社長が10年前から地域と繋がってきてくれたからこそ、『今度○○△△という作業をする予定で…』と言えば、周りの皆さんが色々と手伝ってくれている。本当に有難い」と、桒原さんの義父であり、テール・ド・シエルの社長でもある池田さんと、サポートしてくれている地域の皆さんへの感謝の気持ちを述べられた。サポートが入るとは言え、「手が回らなくなるのも怖い」とも仰る。真摯に畑に向き合っているからこその、誠実な言葉だ。 ▲ 千曲川ワインアカデミー2期生でもある池田さん。ワイナリー社長業に加え、ワイナリーから車で数分の場所にある「Nukaji Wine House(糠地ワインハウス)」を切り盛りしておられる。「外様」と言われたこともあったらしいが、地域との調和を大事に、時間をかけて関係を作り上げてきたそう。この関係性があるからこそ、地域の皆さんが快くワイナリーをサポートして下さるのだ。 相性の良さが分かってきた...
日本ワインコラム | 長野・テール・ド・シエル vol.2
日本ワインコラム | 長野 テール・ド・シエル vol.2 / vol.1 はこちら 約3年ぶり、2度目の来訪となった。 奥行きのあるパノラマの景色、優しく吹き抜ける風、ふかふかの土…何度も立ち止まって深呼吸したくなる場所だ。前回訪問時に味わった感動は全く色褪せることなく、むしろより色濃くなって溢れ出す。何度来ても、「気持ちいい…」という言葉が口に出る、心地の良い空間に佇むのが、テール・ド・シエルの畑と醸造所だ。 ▲ やはりこの場所は何度来ても癒される。じわぁっと体がほぐれていくのだ。 ブドウ栽培、ワイン醸造への真摯な姿勢はそのままに(テール・ド・シエルの成り立ちやワイン造りの考え方についてはVol.1へ)。その上で、3年という月日を経て得た新たな気付きについて、栽培と醸造の責任者を務める桒原さんに色々伺った。 ▲ 前回と変わらない桒原さんの出で立ちに嬉しくなる! 畑は広がっても、きめ細やかな管理を徹底する 元々雑木林だったところを2015年に開墾し始め、10年が経過した。畑は4haまで広がったが、来年は更に60-70a広げ、5ha弱となる見込みだ。開墾する際に気を付けたのは、山を削ることなく、元々の地形をそのまま残すこと。その結果、テール・ド・シエルの畑は色んな方向を向いた様々な角度の斜面となっている。美しい景色が広がるが、急な斜面が多いため機械化は難しく、手作業中心とならざるを得ないし、一枚畑に比べると畑の管理に時間を要するので、栽培者にかかる負荷は大きい。 ▲ 畑の土壌は、7-8割程度を占める粘土質に2-3割程度の火山灰が混ざったもの。千曲川左岸の強粘土質の土壌に比べると、粘土の割合は少ない。 お邪魔した際、1回目の芽かき作業が終わり、誘引を行っているところだった。広い畑なので、1回の芽かきで2-3週間要するという。今年はミノムシが大量発生したそう。ブドウの新芽や葉を食害するのでやっかいな存在だ。これまでに500匹捕殺したとのことだが(驚愕!)、ブドウの収量に影響が出ないよう、1度目の芽かきは慎重に行い、2度目で収量調整を行う予定だという。自然相手の畑で、殺虫剤の使用も極限まで減らしているからこそ、細かい畑の観察とこまめな対策が不可欠なのだ。また、畑では除草剤も使用しないので、草刈りも一仕事。一巡したと思ったら、最初の畑の草は伸びているとのこと。骨の折れる作業を地道に繰り返されているのだ。 ▲ キレイに並ぶブドウの樹。根元も含め、草刈りがしっかりと行われているのがよく分かる。 ▲ 誘引作業により、2本のワイヤーの間に枝がきちんと収まっている。 流石にこの広さを一人で管理しきれないので、地元のシルバーさんに助けてもらっているとのこと。「社長が10年前から地域と繋がってきてくれたからこそ、『今度○○△△という作業をする予定で…』と言えば、周りの皆さんが色々と手伝ってくれている。本当に有難い」と、桒原さんの義父であり、テール・ド・シエルの社長でもある池田さんと、サポートしてくれている地域の皆さんへの感謝の気持ちを述べられた。サポートが入るとは言え、「手が回らなくなるのも怖い」とも仰る。真摯に畑に向き合っているからこその、誠実な言葉だ。 ▲ 千曲川ワインアカデミー2期生でもある池田さん。ワイナリー社長業に加え、ワイナリーから車で数分の場所にある「Nukaji Wine House(糠地ワインハウス)」を切り盛りしておられる。「外様」と言われたこともあったらしいが、地域との調和を大事に、時間をかけて関係を作り上げてきたそう。この関係性があるからこそ、地域の皆さんが快くワイナリーをサポートして下さるのだ。 相性の良さが分かってきた...
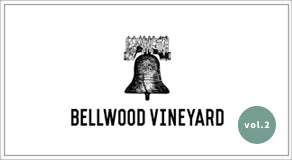
山形・ベルウッド ヴィンヤード ワイナリー vol.2
日本ワインコラム | 山形・ベルウッド ヴィンヤード ワイナリー vol.2 / vol.1 はこちら 山形県上山市の久保手地区にあるベルウッド・ヴィンヤード。前回お邪魔したのは、ちょうどワイナリーが完成した年だったので、約5年前になる。あの時と変わらぬ、ぱっと目を引くスタイリッシュな鈴木さん。そして、木材とテーマカラーの黒を掛け合わせ造られたワイナリーの洗練された雰囲気も変わらない。 ▲ 木材をふんだんに使いつつ、黒で締めることで、武骨でインダストリアルな雰囲気のあるワイナリー。 大きく異なるのは外の景色。前回は初冬に訪問したが、今回は猛暑真っ只中。一歩外に出れば汗ぐっしょりで、人間は日差しの強さに負けそうになるが、その分、逞しく成長しているブドウの生命力の強さを感じる。5年という年月を経て、細かったブドウの樹も大きく成長し、青々とした葉っぱを茂らせ、元気一杯だ。鈴木さんもちょっとのことでは動じない、ある種余裕さえ感じる佇まいだ。いい意味での脱力感はありつつ、スパっと行動に移す軽やかさがある。鈴木さんの造るワインに感じる洒脱さは、やはり鈴木さんの人柄が滲み出ているのだろう。 好き→アンテナが伸びる→センスが磨かれる 鈴木さんの周りは、どこを切り取っても洒落ている。ご本人の風貌はもちろんのこと、持ち物、ワイナリー内のディスプレイ、ワインのラベル、そしてその味わいさえも。近寄りがたさのある尖ったオシャレではなく、居心地のよさを感じるオシャレだ。 ▲ ワイナリー内には、鈴木さんの審美眼に選ばれたアウトドアグッズが飾れている。 前回訪問時に、 「独立してからは、何を置くにしても、周囲には自分の好きなものだけを置くように、それだけは曲げたくないと思っています。ラベルにしても何にしても、ひとつひとつを、自分を表現する一部として考えているのです。」 と答えられていたように、やはりご自身の「好き」が集まった空間には、ジャンルが違っても統一感があるし、どれを取っても「鈴木さん」を感じるのだ。 きっと、ワインも「好き」を大事にして始められたのかと思いきや、意外な歴史を教えてくれた。 「山形県朝日町出身で、高校卒業後、仙台の専門学校に進学したのですが、留年して…卒業後もなかなか進路が決まらなくて。そしたら、親が知らない間に朝日町ワインに履歴書を送っていて、「ここに入れ」と言われるままに就職したんです(苦笑)。」 なんともビックリだ。若かりし頃の鈴木さんは、「やりたいことがわからない」というモヤモヤした不安みたいなものがあったのだろうか…それにしても、ご両親のアシストがなければワインの道に進んでいなかった訳なので、感謝してもしきれない。きっと、鈴木さんの好みをある程度理解した上で、半ば強引に道を作ってくれたのではないだろうか。 ▲ 本当、ワインの道に進んでくれた良かったです~!! 鈴木さんのぶっちゃけはここで止まらない。「折角朝日町ワインに就職したんですが、余暇の遊びが楽しくて、そっちで生計を立てようかと思ったこともある」、と言うではないか‼破天荒ぶりに思考停止になりそうになるが、見逃してはいけないのが、趣味を仕事にしようと思う程上達したという点だ。鈴木さんは、好きになるとアンテナがぐぃ~んと人一倍伸びるのだ。有難いことに、ワインの道は残った。「趣味にお金を使い果たした(笑)」ということもあるそうだが、それだけではない。スタートがどうであれ、毎日ワイン造りに向き合う内に、「好き」が蓄積されたのだろう。そして、アンテナが伸びた。その結果、ご自身が製造に携わったワインが、コンクールで金賞を受賞するまでセンスが磨かれたのだ。そうなると、自分のセンスを追求して試したくなるものだ。19年間働いた朝日町ワインを卒業し、2017年に自分で栽培から醸造まで手掛けるスタイルに移行する。こうして、誕生したのがベルウッド・ヴィンヤードなのだ。 自分を枯渇させないから可能な挑戦 鈴木さんの牧歌的な口調も影響しているかもしれないが、鈴木さんからは苦しさが感じられない。もちろん、夏場は朝4時台に起床、5時台には畑に出て、日が暮れる19時30分頃まで畑仕事、その後事務仕事が21時頃まで続くというのだから、フル回転だ。「手が回りきらない」と呟かれるが、疲弊感はないし、何となく楽しそうなのだ。なぜだろう? 10から10+αの結果を引き出す ワイナリーのすぐ隣に1ha弱の自社畑が広がる。周囲は平らな田畑が広がるが、畑は独立峰のような形で隆起した小高い丘になっている。もともと耕作放棄地だった場所を、2017年の独立と同時に垣根仕立てで複数の欧州品種を植樹した場所だ。もう一つの畑は、ワイナリーから500mほど離れた場所にある10a弱の畑。後継者のいないデラウェアの畑を引き継ぎ、棚仕立てで有核栽培している。無理をすれば畑を広げられるかもしれないが、鈴木さん、今ある畑をきっちり管理することに重点を置いている。...
山形・ベルウッド ヴィンヤード ワイナリー vol.2
日本ワインコラム | 山形・ベルウッド ヴィンヤード ワイナリー vol.2 / vol.1 はこちら 山形県上山市の久保手地区にあるベルウッド・ヴィンヤード。前回お邪魔したのは、ちょうどワイナリーが完成した年だったので、約5年前になる。あの時と変わらぬ、ぱっと目を引くスタイリッシュな鈴木さん。そして、木材とテーマカラーの黒を掛け合わせ造られたワイナリーの洗練された雰囲気も変わらない。 ▲ 木材をふんだんに使いつつ、黒で締めることで、武骨でインダストリアルな雰囲気のあるワイナリー。 大きく異なるのは外の景色。前回は初冬に訪問したが、今回は猛暑真っ只中。一歩外に出れば汗ぐっしょりで、人間は日差しの強さに負けそうになるが、その分、逞しく成長しているブドウの生命力の強さを感じる。5年という年月を経て、細かったブドウの樹も大きく成長し、青々とした葉っぱを茂らせ、元気一杯だ。鈴木さんもちょっとのことでは動じない、ある種余裕さえ感じる佇まいだ。いい意味での脱力感はありつつ、スパっと行動に移す軽やかさがある。鈴木さんの造るワインに感じる洒脱さは、やはり鈴木さんの人柄が滲み出ているのだろう。 好き→アンテナが伸びる→センスが磨かれる 鈴木さんの周りは、どこを切り取っても洒落ている。ご本人の風貌はもちろんのこと、持ち物、ワイナリー内のディスプレイ、ワインのラベル、そしてその味わいさえも。近寄りがたさのある尖ったオシャレではなく、居心地のよさを感じるオシャレだ。 ▲ ワイナリー内には、鈴木さんの審美眼に選ばれたアウトドアグッズが飾れている。 前回訪問時に、 「独立してからは、何を置くにしても、周囲には自分の好きなものだけを置くように、それだけは曲げたくないと思っています。ラベルにしても何にしても、ひとつひとつを、自分を表現する一部として考えているのです。」 と答えられていたように、やはりご自身の「好き」が集まった空間には、ジャンルが違っても統一感があるし、どれを取っても「鈴木さん」を感じるのだ。 きっと、ワインも「好き」を大事にして始められたのかと思いきや、意外な歴史を教えてくれた。 「山形県朝日町出身で、高校卒業後、仙台の専門学校に進学したのですが、留年して…卒業後もなかなか進路が決まらなくて。そしたら、親が知らない間に朝日町ワインに履歴書を送っていて、「ここに入れ」と言われるままに就職したんです(苦笑)。」 なんともビックリだ。若かりし頃の鈴木さんは、「やりたいことがわからない」というモヤモヤした不安みたいなものがあったのだろうか…それにしても、ご両親のアシストがなければワインの道に進んでいなかった訳なので、感謝してもしきれない。きっと、鈴木さんの好みをある程度理解した上で、半ば強引に道を作ってくれたのではないだろうか。 ▲ 本当、ワインの道に進んでくれた良かったです~!! 鈴木さんのぶっちゃけはここで止まらない。「折角朝日町ワインに就職したんですが、余暇の遊びが楽しくて、そっちで生計を立てようかと思ったこともある」、と言うではないか‼破天荒ぶりに思考停止になりそうになるが、見逃してはいけないのが、趣味を仕事にしようと思う程上達したという点だ。鈴木さんは、好きになるとアンテナがぐぃ~んと人一倍伸びるのだ。有難いことに、ワインの道は残った。「趣味にお金を使い果たした(笑)」ということもあるそうだが、それだけではない。スタートがどうであれ、毎日ワイン造りに向き合う内に、「好き」が蓄積されたのだろう。そして、アンテナが伸びた。その結果、ご自身が製造に携わったワインが、コンクールで金賞を受賞するまでセンスが磨かれたのだ。そうなると、自分のセンスを追求して試したくなるものだ。19年間働いた朝日町ワインを卒業し、2017年に自分で栽培から醸造まで手掛けるスタイルに移行する。こうして、誕生したのがベルウッド・ヴィンヤードなのだ。 自分を枯渇させないから可能な挑戦 鈴木さんの牧歌的な口調も影響しているかもしれないが、鈴木さんからは苦しさが感じられない。もちろん、夏場は朝4時台に起床、5時台には畑に出て、日が暮れる19時30分頃まで畑仕事、その後事務仕事が21時頃まで続くというのだから、フル回転だ。「手が回りきらない」と呟かれるが、疲弊感はないし、何となく楽しそうなのだ。なぜだろう? 10から10+αの結果を引き出す ワイナリーのすぐ隣に1ha弱の自社畑が広がる。周囲は平らな田畑が広がるが、畑は独立峰のような形で隆起した小高い丘になっている。もともと耕作放棄地だった場所を、2017年の独立と同時に垣根仕立てで複数の欧州品種を植樹した場所だ。もう一つの畑は、ワイナリーから500mほど離れた場所にある10a弱の畑。後継者のいないデラウェアの畑を引き継ぎ、棚仕立てで有核栽培している。無理をすれば畑を広げられるかもしれないが、鈴木さん、今ある畑をきっちり管理することに重点を置いている。...
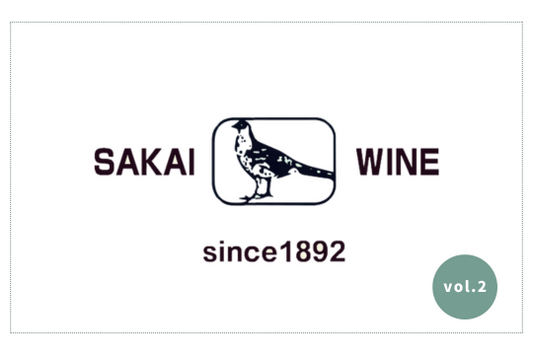
山形・酒井ワイナリー vol.2
日本ワインコラム |酒井ワイナリー/ Vol.2 / vol.1 はこちら 初めて酒井ワイナリー5代目当主の酒井一平さんを取材したのは約5年前。クロード・レヴィ=ストロースが唱えた構造主義や、同氏の代表作『野生の思考』の中で紹介されている「ブリコラージュ(日曜大工)」という概念を織り交ぜながら、ご自身のワイン造りについて語ってくれた。 今回も、ちょっと小難しい…(すみません!汗)、もとい、哲学的で思索的な印象はそのままに、更なるステージへ足を踏み入れている姿をみせてくれた。他のワイナリーの方々と話をしていると、酒井さんを「超人的」と評されるのをよく耳にする。点在する耕作放棄地を管理するだけでも大変なのに、化学農薬、殺虫剤、化学肥料、除草剤無しでブドウを栽培。そして、東北最古のワイナリーの当主という立場もあってか、様々な役職にも付いている。確固たる信念があるからこその行動だとは思うが、なかなかできないことだ。 今回は、そんな「超人的な」酒井さんの考え方の軸となる部分や現在の様子、そして今後の展望や課題について話を伺った。 ▲ 絵本に出てきそうな愛らしさのワイナリー外観。ワイナリーは赤湯温泉街にあり、そぞろ歩きも楽しめる。 『その土地の普通』を追い求めて 酒井ワイナリーは、1892年創業の東北で最も長い歴史を持つワイナリーだ。2004年に酒井さんが5代目を継いで20年強が経過している。今でこそ、「酒井ワイナリー=自然な造りのワイン」というイメージを持っておられる方が多いと思うが、化学農薬、殺虫剤、化学肥料、除草剤無しでブドウを育て、野生酵母で発酵し、無清澄・無濾過、亜硫酸は極少量ないし無添加でワインに仕上げる、という全行程が確立したのは、5代目になってからである。このスタイルに行きついた背景には何があるのだろうか? ▲ ワイナリーの中に貼られている酒井ワイナリーの歴史。 昔、(ドメーヌ・オヤマダの)小山田さんが主宰していた若手勉強会に参加した際に、自分で醸造したワインを持って行ったことがあるんです。『どうやって造ったの?』と聞かれたので、『普通に造りました』と答えたら、『普通って何?』って聞かれたんです。その時に絶句してしまって。自分の言う『普通』って何なんだろう?と凄く考えるようになりました。そこから、様々な書物を読んだりして自分なりに思考を深めたんです。 こんな禅問答がある勉強会に恐ろしさを感じなくもないが、この出来事をきっかけに、構造主義を始めとする哲学書や自然科学の本を読み漁るというところが、酒井さんが酒井さんたる所以なのかもしれない。 ▲ 深い思考を重ねた上で、ワイン造りに向き合う酒井さん。 『その土地における普通のワインとは何だ?』という問いを突き付けられたと考え、そこから、『その土地における文化的普遍性とは何か?』と考えを深めました。そして、自分の中で辿り着いた答えが、『その地域における自然の有り様』だったのです。自然は一定ではなく、万物流転で変化し続けますが、その中でその土地特有のものが生まれます。 ▲ 酒井さんのインスタより。畑の草刈りをしている時にヨシキリの巣を発見したとのこと。畑には多様な生き物が生息しているのだ。 その上で、ブドウ栽培における酒井さんの考えが続く。 だから、例えば自分の畑は『ブドウ畑』とは思っていません。牧草も植えているし、桜を始めとした色んな木が植わっています。あらゆる生き物の力に頼った畑なのです。畑にブドウと人間しかいないというのは不自然、つまりその土地の農作物ではなくなり、普遍性から離れる。だから除草剤や殺虫剤を用いて、微生物を始めとする生き物を殺すことはしない。たとえ、出来上がるブドウがどんなにきれいでも。畑の環境も森に近づけたいと思っています。 ワイン醸造においても、この考えが根底にある。 「ワインを野生酵母で発酵するのは、野生酵母で造った方が美味しいからという理由ではなくて、その土地で全てを自給することで初めて、その土地のブドウやワインの文化ができると考えているからです。ルイ・パスツールの発見によってワインは高品質且つ安定的なものになったかもしれないが、同時に優生的な思想を生み出した。ここから離れるべきだと考えています。」 因みに、ルイ・パスツールは「細菌学の父」と言われる偉大な人物で、アルコール発酵が酵母によるものだと発見したり、ワインの腐敗を防ぐため、微生物を殺菌する低温殺菌法を生み出したりした人物で、現代のワイン造りの父と言える人物だ。酒井さんの「優生的な思想から離れるべき」というのは、微生物をすべからく悪と考える思想にNOと言いたいということだろう。 「ワインはその土地を知る最良の方法の一つ」と酒井さんは言う。ヴィンテージ差もあるし、土地と品種の相性もある。造り手の思想も反映されやすい。そして、土地の歴史を感じるものでもある。例えば、赤湯は今でこそデラウェアの生産量は隣の高畠町より少ないが、長く日本一を誇っていた。土地の微生物を含め、栽培環境とデラウェアを始めとするブドウ栽培がマッチしているのだ。 全ては循環する ー ミッシングリンクは動物だった 酒井ワイナリーの近辺には3つの山がある—...
山形・酒井ワイナリー vol.2
日本ワインコラム |酒井ワイナリー/ Vol.2 / vol.1 はこちら 初めて酒井ワイナリー5代目当主の酒井一平さんを取材したのは約5年前。クロード・レヴィ=ストロースが唱えた構造主義や、同氏の代表作『野生の思考』の中で紹介されている「ブリコラージュ(日曜大工)」という概念を織り交ぜながら、ご自身のワイン造りについて語ってくれた。 今回も、ちょっと小難しい…(すみません!汗)、もとい、哲学的で思索的な印象はそのままに、更なるステージへ足を踏み入れている姿をみせてくれた。他のワイナリーの方々と話をしていると、酒井さんを「超人的」と評されるのをよく耳にする。点在する耕作放棄地を管理するだけでも大変なのに、化学農薬、殺虫剤、化学肥料、除草剤無しでブドウを栽培。そして、東北最古のワイナリーの当主という立場もあってか、様々な役職にも付いている。確固たる信念があるからこその行動だとは思うが、なかなかできないことだ。 今回は、そんな「超人的な」酒井さんの考え方の軸となる部分や現在の様子、そして今後の展望や課題について話を伺った。 ▲ 絵本に出てきそうな愛らしさのワイナリー外観。ワイナリーは赤湯温泉街にあり、そぞろ歩きも楽しめる。 『その土地の普通』を追い求めて 酒井ワイナリーは、1892年創業の東北で最も長い歴史を持つワイナリーだ。2004年に酒井さんが5代目を継いで20年強が経過している。今でこそ、「酒井ワイナリー=自然な造りのワイン」というイメージを持っておられる方が多いと思うが、化学農薬、殺虫剤、化学肥料、除草剤無しでブドウを育て、野生酵母で発酵し、無清澄・無濾過、亜硫酸は極少量ないし無添加でワインに仕上げる、という全行程が確立したのは、5代目になってからである。このスタイルに行きついた背景には何があるのだろうか? ▲ ワイナリーの中に貼られている酒井ワイナリーの歴史。 昔、(ドメーヌ・オヤマダの)小山田さんが主宰していた若手勉強会に参加した際に、自分で醸造したワインを持って行ったことがあるんです。『どうやって造ったの?』と聞かれたので、『普通に造りました』と答えたら、『普通って何?』って聞かれたんです。その時に絶句してしまって。自分の言う『普通』って何なんだろう?と凄く考えるようになりました。そこから、様々な書物を読んだりして自分なりに思考を深めたんです。 こんな禅問答がある勉強会に恐ろしさを感じなくもないが、この出来事をきっかけに、構造主義を始めとする哲学書や自然科学の本を読み漁るというところが、酒井さんが酒井さんたる所以なのかもしれない。 ▲ 深い思考を重ねた上で、ワイン造りに向き合う酒井さん。 『その土地における普通のワインとは何だ?』という問いを突き付けられたと考え、そこから、『その土地における文化的普遍性とは何か?』と考えを深めました。そして、自分の中で辿り着いた答えが、『その地域における自然の有り様』だったのです。自然は一定ではなく、万物流転で変化し続けますが、その中でその土地特有のものが生まれます。 ▲ 酒井さんのインスタより。畑の草刈りをしている時にヨシキリの巣を発見したとのこと。畑には多様な生き物が生息しているのだ。 その上で、ブドウ栽培における酒井さんの考えが続く。 だから、例えば自分の畑は『ブドウ畑』とは思っていません。牧草も植えているし、桜を始めとした色んな木が植わっています。あらゆる生き物の力に頼った畑なのです。畑にブドウと人間しかいないというのは不自然、つまりその土地の農作物ではなくなり、普遍性から離れる。だから除草剤や殺虫剤を用いて、微生物を始めとする生き物を殺すことはしない。たとえ、出来上がるブドウがどんなにきれいでも。畑の環境も森に近づけたいと思っています。 ワイン醸造においても、この考えが根底にある。 「ワインを野生酵母で発酵するのは、野生酵母で造った方が美味しいからという理由ではなくて、その土地で全てを自給することで初めて、その土地のブドウやワインの文化ができると考えているからです。ルイ・パスツールの発見によってワインは高品質且つ安定的なものになったかもしれないが、同時に優生的な思想を生み出した。ここから離れるべきだと考えています。」 因みに、ルイ・パスツールは「細菌学の父」と言われる偉大な人物で、アルコール発酵が酵母によるものだと発見したり、ワインの腐敗を防ぐため、微生物を殺菌する低温殺菌法を生み出したりした人物で、現代のワイン造りの父と言える人物だ。酒井さんの「優生的な思想から離れるべき」というのは、微生物をすべからく悪と考える思想にNOと言いたいということだろう。 「ワインはその土地を知る最良の方法の一つ」と酒井さんは言う。ヴィンテージ差もあるし、土地と品種の相性もある。造り手の思想も反映されやすい。そして、土地の歴史を感じるものでもある。例えば、赤湯は今でこそデラウェアの生産量は隣の高畠町より少ないが、長く日本一を誇っていた。土地の微生物を含め、栽培環境とデラウェアを始めとするブドウ栽培がマッチしているのだ。 全ては循環する ー ミッシングリンクは動物だった 酒井ワイナリーの近辺には3つの山がある—...

山形・高畠ワイナリー
日本ワインコラム |高畠ワイナリー 夏休みが始まるこの時期。一年で一番暑いとされる大暑入りが前日に発表されただけあり、インタビュー当日も朝から異常に暑い!!東北地方だから暑さはマシだろうなんて思うのは大きな間違い。山形県は四方を山で囲まれた山形盆地により、熱が溜まりやすい環境にある。そして、1933年に40.8℃という気温を出し、2007年までの74年間、日本の観測史上最高気温を誇った場所でもあるのだ。 そんな山形盆地から南に下り、置賜というエリアにあるのが、今回のインタビューのお相手の所在地、高畠町だ。『まほろば(「周囲を山に囲まれた平地で、住みよい美しいところ」という意味)の里』と呼ばれる町で、平坦部では稲作が、山間部ではブドウなどの果樹が栽培される実り豊かな土地である。しかーし、置賜も盆地なので、夏は暑い!朝からお邪魔したが、一瞬にして滝汗が流れる…。 今回は、そんな暑さをものともしない、高畠ワイナリーの皆さんが目指すワイン造りについて話を聞いてきた。 ▲ 赤い屋根が目を引く建物。 ▲ ワイン樽を使った看板を見るだけで、ワインが飲みたくなる。笑 ワイナリー名に込められた思い 高畠は四方を山々に囲まれた置賜盆地の南部に位置する。山間部を利用する形でブドウ栽培が始まったのは、明治時代。欧州系ブドウが試験栽培されたが、ヨーロッパとの栽培環境の違いや当時の技術力では栽培が難しく、広がりは見せなかった。しかし、明治から大正にかけて始まったデラウェアの栽培が大成功。今では、日本一のデラウェアの産地として知られるほどに成長している。成功のカギとなったのが高畠という栽培環境だ。夏から秋にかけて盆地特有の昼夜の寒暖差が大きく、ブドウ栽培に適している。また、4月から10月のブドウ生育期間の降水量は800-900mmと比較的少ない。更に、海底から隆起した山間部の地層には、海洋生物の化石が多く、ミネラル分も豊富。排水と保水のバランスが良いのだ。 ▲ 羊のようなモコモコした白い雲と水色の空、緑が美しい田んぼ、そして遠目の山々!なんて美しい景色…。 そんな生食用ブドウ栽培の歴史が長い置賜地区で、初の「観光ワイナリー」として1990年に誕生したのが、高畠ワイナリーだ。当時の親会社(南九州コカ・コーラボトリング)が塩尻市で「太田葡萄酒」を運営していたが、住宅街で手狭になったこともあり、酒造免許を移転する形で高畠ワイナリーが誕生したのだ。設立当初は、高畠町産のブドウと海外からの輸入原料を合わせたワイン造りだったが、徐々に地元産原料に軸足を移し、現在は63軒の契約農家を中心にブドウを仕入れる他、自社畑での栽培にも力を入れるようになっている。 ▲ 皆さん、こちらの会社のポロシャツをお召しになっていました!なんかいいな~。 ブドウの栽培環境がワインの味わいに与える影響が大きいのは周知の事実だが、地名を名称に付しているワイナリーの数はそこまで多くはない。そんな中、高畠ワイナリーが「高畠」という地名を明確に打ち出しているのは、「高畠」の認知度を上げたい、ブドウ産地として盛り上げたい、そして観光の拠点としても活性化していきたいという思いの表れ。『「高畠」を世界のワイン産地の一つにする』という大きな使命を掲げ、ワイン造りに向き合っているのだ。 長く続く契約農家との関係 ワイナリーで仕込むブドウの量は年間約460トンと大量だ。もっとも、農業法人としてではなく、醸造を軸に事業がスタートしたという経緯もあり、国産原料のうち、自社ブドウは4%程度で、殆どは契約農家を中心とする買いブドウでワインを仕込んでいる。共存関係が始まったのは、1991年。昔から生食用のブドウ栽培を続ける農家の知見を活かしたいと、「高畠ワインブドウ部会」を立ち上げ、契約農家と共に醸造用ブドウの栽培に取り組んだ。目を付けたのは、デラウェア栽培で昔から培われてきた雨除けハウス(サイドレス)の棚仕立て。側面がオープンになっているので、雨除けしつつ適度な水分ストレスを与えると共に、通気性を確保できる栽培方法で、質の高いブドウが収穫できると分かり、現在も採用している。27名でスタートした契約農家との共存関係は、今では63軒まで増加。長い時間をかけ、信頼関係を築いていることが分かるだろう。 ▲ 高畠ワイナリーHPより。上面のみビニールが張っているのが分かる。 問題が全くないという訳ではない。 2024年は特に雪が多くて、サイドレスハウスが壊れたところも多かった。では、高齢化している農家が大枚をはたいてハウスを修理するかというと、そうとも限らない。これを機に農家を引退する人が多い と営業部長の木村さんが実情を教えてくれた。 農家と二人三脚で歩んできた高畠ワイナリーにとって、農家の高齢化や離農は難しい課題だ。そのような背景も多少影響しているのだろう、高畠ワイナリーでは自社畑を拡充しつつある。次章で詳しく見てみたい。 大量生産と真逆のワイン造りを目指して~自社畑での取り組み 高畠ワイナリーは2012年、大量生産と真逆のワイン造りを掲げ、自分達で手間暇をかけてブドウを栽培し、自社ブドウから質の高いワインを造ろうと「Garagiste Winery(ガレージステ・ワイナリー)構想」を立ち上げた。中でも、上質なボルドースタイルの赤ワイン造りを目指し、準備を進めてきている。畑ではどういった取り組みをしてきたのだろう?原料栽培担当の四釜さんに色々と話を伺った。 ▲ 「好きな作業は、今後を考えながら行う剪定。嫌いな作業は、終わりの見えない誘引。一日で色んな畑に行くことができるので、意外に草刈りも好き」、と話してくれた四釜さん。優しい笑顔と控え目な人柄に温かみを感じる。...
山形・高畠ワイナリー
日本ワインコラム |高畠ワイナリー 夏休みが始まるこの時期。一年で一番暑いとされる大暑入りが前日に発表されただけあり、インタビュー当日も朝から異常に暑い!!東北地方だから暑さはマシだろうなんて思うのは大きな間違い。山形県は四方を山で囲まれた山形盆地により、熱が溜まりやすい環境にある。そして、1933年に40.8℃という気温を出し、2007年までの74年間、日本の観測史上最高気温を誇った場所でもあるのだ。 そんな山形盆地から南に下り、置賜というエリアにあるのが、今回のインタビューのお相手の所在地、高畠町だ。『まほろば(「周囲を山に囲まれた平地で、住みよい美しいところ」という意味)の里』と呼ばれる町で、平坦部では稲作が、山間部ではブドウなどの果樹が栽培される実り豊かな土地である。しかーし、置賜も盆地なので、夏は暑い!朝からお邪魔したが、一瞬にして滝汗が流れる…。 今回は、そんな暑さをものともしない、高畠ワイナリーの皆さんが目指すワイン造りについて話を聞いてきた。 ▲ 赤い屋根が目を引く建物。 ▲ ワイン樽を使った看板を見るだけで、ワインが飲みたくなる。笑 ワイナリー名に込められた思い 高畠は四方を山々に囲まれた置賜盆地の南部に位置する。山間部を利用する形でブドウ栽培が始まったのは、明治時代。欧州系ブドウが試験栽培されたが、ヨーロッパとの栽培環境の違いや当時の技術力では栽培が難しく、広がりは見せなかった。しかし、明治から大正にかけて始まったデラウェアの栽培が大成功。今では、日本一のデラウェアの産地として知られるほどに成長している。成功のカギとなったのが高畠という栽培環境だ。夏から秋にかけて盆地特有の昼夜の寒暖差が大きく、ブドウ栽培に適している。また、4月から10月のブドウ生育期間の降水量は800-900mmと比較的少ない。更に、海底から隆起した山間部の地層には、海洋生物の化石が多く、ミネラル分も豊富。排水と保水のバランスが良いのだ。 ▲ 羊のようなモコモコした白い雲と水色の空、緑が美しい田んぼ、そして遠目の山々!なんて美しい景色…。 そんな生食用ブドウ栽培の歴史が長い置賜地区で、初の「観光ワイナリー」として1990年に誕生したのが、高畠ワイナリーだ。当時の親会社(南九州コカ・コーラボトリング)が塩尻市で「太田葡萄酒」を運営していたが、住宅街で手狭になったこともあり、酒造免許を移転する形で高畠ワイナリーが誕生したのだ。設立当初は、高畠町産のブドウと海外からの輸入原料を合わせたワイン造りだったが、徐々に地元産原料に軸足を移し、現在は63軒の契約農家を中心にブドウを仕入れる他、自社畑での栽培にも力を入れるようになっている。 ▲ 皆さん、こちらの会社のポロシャツをお召しになっていました!なんかいいな~。 ブドウの栽培環境がワインの味わいに与える影響が大きいのは周知の事実だが、地名を名称に付しているワイナリーの数はそこまで多くはない。そんな中、高畠ワイナリーが「高畠」という地名を明確に打ち出しているのは、「高畠」の認知度を上げたい、ブドウ産地として盛り上げたい、そして観光の拠点としても活性化していきたいという思いの表れ。『「高畠」を世界のワイン産地の一つにする』という大きな使命を掲げ、ワイン造りに向き合っているのだ。 長く続く契約農家との関係 ワイナリーで仕込むブドウの量は年間約460トンと大量だ。もっとも、農業法人としてではなく、醸造を軸に事業がスタートしたという経緯もあり、国産原料のうち、自社ブドウは4%程度で、殆どは契約農家を中心とする買いブドウでワインを仕込んでいる。共存関係が始まったのは、1991年。昔から生食用のブドウ栽培を続ける農家の知見を活かしたいと、「高畠ワインブドウ部会」を立ち上げ、契約農家と共に醸造用ブドウの栽培に取り組んだ。目を付けたのは、デラウェア栽培で昔から培われてきた雨除けハウス(サイドレス)の棚仕立て。側面がオープンになっているので、雨除けしつつ適度な水分ストレスを与えると共に、通気性を確保できる栽培方法で、質の高いブドウが収穫できると分かり、現在も採用している。27名でスタートした契約農家との共存関係は、今では63軒まで増加。長い時間をかけ、信頼関係を築いていることが分かるだろう。 ▲ 高畠ワイナリーHPより。上面のみビニールが張っているのが分かる。 問題が全くないという訳ではない。 2024年は特に雪が多くて、サイドレスハウスが壊れたところも多かった。では、高齢化している農家が大枚をはたいてハウスを修理するかというと、そうとも限らない。これを機に農家を引退する人が多い と営業部長の木村さんが実情を教えてくれた。 農家と二人三脚で歩んできた高畠ワイナリーにとって、農家の高齢化や離農は難しい課題だ。そのような背景も多少影響しているのだろう、高畠ワイナリーでは自社畑を拡充しつつある。次章で詳しく見てみたい。 大量生産と真逆のワイン造りを目指して~自社畑での取り組み 高畠ワイナリーは2012年、大量生産と真逆のワイン造りを掲げ、自分達で手間暇をかけてブドウを栽培し、自社ブドウから質の高いワインを造ろうと「Garagiste Winery(ガレージステ・ワイナリー)構想」を立ち上げた。中でも、上質なボルドースタイルの赤ワイン造りを目指し、準備を進めてきている。畑ではどういった取り組みをしてきたのだろう?原料栽培担当の四釜さんに色々と話を伺った。 ▲ 「好きな作業は、今後を考えながら行う剪定。嫌いな作業は、終わりの見えない誘引。一日で色んな畑に行くことができるので、意外に草刈りも好き」、と話してくれた四釜さん。優しい笑顔と控え目な人柄に温かみを感じる。...
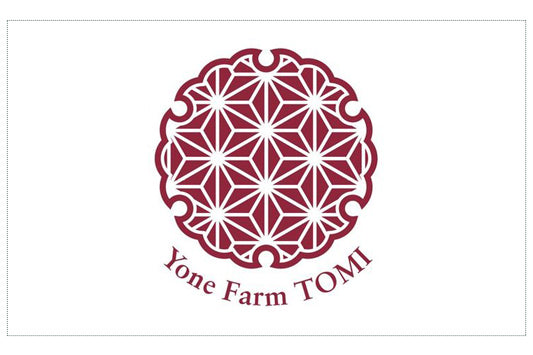
長野・ヨネファーム東御
日本ワインコラム |ヨネファーム東御 インタビューのお相手、米倉さんとは、地元で大人気のやきそば・ワンタンのお店「開花亭」で待ち合わせ。到着時には既に長い行列だったが、食い意地の張った我々にとって行列なんて怖くない。米倉さんへのご挨拶も早々に、熱々の焼きそばとワンタンを汗タラタラで食すところからのスタートとなった。こんな素敵なお店での待ち合わせを提案して下さったくらいだし、さぞかし何度も来店しているかと思いきや、2回目という米倉さん。普段はきっと、畑仕事が忙しくて、のんびりランチとはいかないのだろう… ▲ くしゃっとした目元が印象的。優しい笑顔の米倉さん。 2018年に東御市でワイン用ブドウ栽培を開始した米倉さんは、3ヶ所に跨る約5haの畑で多種多様なブドウ品種を一人で栽培するスーパーマンだ。口数は少なめ。反射神経的に言葉を発するのではなく、自分の中で納得したことだけを話すからだろう。だからこそ、発せられる言葉には強い意志を感じる。そんな米倉さんの現在とこれからについて色々とお話を伺った。 広がる畑の管理 米倉さんがワイン業界に足を踏み入れたのは50歳を目前にした頃。その前から15年間毎月ワイン会を開催し、友人達と世界各地のワインを楽しんだり、ブルゴーニュ、ローヌ、カリフォルニアといった銘醸地を訪問し、栽培・醸造を体験したりと、趣味以上仕事未満の熱量でワインと関わってきたが、とうとう仕事にする決意を固め、25年勤務した通信系会社を退職。2015年に東京、神楽坂でワインバー&ショップをオープンしたが、ワインとの関係が深まる中でワイン造りへの興味が増し、開店数年で再度転身を図る。長野県東御市が募集していた千曲川ワインアカデミーの3期生として、2017年に移住するのだ。そして、信州うえだファームの研修生として農業研修も受け、2019年に独立する。 ▲ ヨネファーム東御のインスタより。千曲川ワインアカデミーの同期との一枚。いい関係性なのが見て取れる素敵な一枚だ。 米倉さんのブドウ畑は、長野県東御市の3つの場所(鞍掛金井、祢津御堂、海善寺)に跨る。東御市は降水量が少なく、冷涼ながら日照時間は長い。また、畑は540mから780mと標高が高い場所にあり、昼夜の寒暖差のあるワイン用ブドウ栽培に恵まれた場所だ。 独立後すぐに植栽開始したのは鞍掛金井。0.5haの広さに白赤6種類のブドウが植わっている。その後、巨峰が植わる海善寺の畑の管理も開始し、2019年には、東御市がワイン用ブドウ団地として立ち上げた祢津御堂での植栽を開始する。広さ4.1haの畑で、赤白11種類のブドウを栽培している。これだけではない。畑に足を運ぶことが難しくなった千曲川ワインアカデミー同期の0.7haの畑の管理もお手伝いしているというのだから、どこにそんな体力があるのか…⁉と目が点になる。 持続可能なブドウ栽培を目指して 「できるだけ薬は使いたくはないけど、ブドウができないと話にならない」、と米倉さんは語る。東御市はワイン用ブドウ栽培に適した場所ではあるが、「日本の中で」という前提が付く。高温多湿な日本は、世界の銘醸地と比べてブドウが病気にかかるリスクは格段に高い。ブドウ栽培を始めてから3年目までは年3回程度の農薬散布で問題なかったが、4年目になると一気に病気が蔓延して大変な事態に陥ったそうだ。リュー・ド・ヴァンの小山さんも同じことを語っていたが、若木は菌やウイルスの蓄積がなく、無農薬でも大きな問題にはならないことが多いが、年数を重ねるにつれ、病原物質が蓄積され病気が発生しやすくなるのだ。 こういった経験も踏まえ、ビジネスと環境の両立の観点から減農薬栽培を主軸に据え、農薬散布量はJAの防除暦で推奨される量の半分程度に抑えているそうだ。 ▲ 祢津御堂にある米倉さんの畑の様子。眼下に市街地が見え、遠くには八ヶ岳、霧ヶ峰、北アルプスといった美しい山々の絶景が!また、畑の前にはビジターセンターである「ワインテラス御堂」があり、ワインの試飲・販売スペースもある。 気候変動の影響だろうか、極端な空模様になることが増えた昨今。これまでとは異なる対策が求められつつある。2024年は猛暑に加え、8月後半から9月にかけて雨が断続的に降り続く難しい年で、収穫前に一気に晩腐病というカビの病気が広がったそうだ。特に黒ブドウへの影響が大きく、収量は予定の半分程度、メルロに至っては9割方がダメになってしまった。今後も異常気象が続くと言われており、農家にとっては困難な時代だ。米倉さんの畑では雨除けは特に必要としてこなかったが、今年からは祢津御堂のメルロについては、フルーツゾーンだけの雨除けを始める予定だそう。薬に頼らない対策を色々と考えておられるのだ。 ▲ 祢津御堂の畑は、緩やかな斜面だ。広いスペースなので草刈りだけでも本当に大変… 一つに絞るのはもったいない 3つの畑では、白ブドウ6品種(シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン、リースリング、セミヨン、ルーサンヌ、ヴィオニエ)、黒ブドウ9種類(シラー、ムールヴェルドル、グルナッシュ、メルロ、カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨン、プティ・ヴェルド、ピノ・ノワール、巨峰)と、多種多様なブドウを育てている。これらはフランスの主なワイン品種であると同時に、世界的にも認知度が高い。 「品種それぞれに美味しさがある。1つに絞るのはもったいないし、決められない」、と米倉さんは言う。ワインに対する深い愛情を感じる言葉だ。これまでは、各品種の収量が少ないということもありブレンドすることが多かったが、いざブレンドしてみると、ブレンドしたからこそ得られる美味しさや組み合わせによる新たな発見もあり、手応えを感じている。 例えば、「メランジュ・ボルドレーズ」というキュヴェでは、ボルドー・ブレンドとして、メルロ、カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨン、プティ・ヴェルドといった品種がブレンドされているし、「メランジュ・ローダニアン」は、ローヌ地方のワインを彷彿とさせる、シラーとムールヴェルドルのブレンドに仕上がっている。品種や比率は毎年変わるが、こういった楽しさが提供できるのは、多品種を育てているからこそ。 ▲ 千曲川ワインアカデミーの同期と立ち上げたブランド「トロワジエーム」の名を冠したオンラインストア、「トロワジエーム・ワインズ」より。左が「メランジュ・ボルドレーズ」、右が「メランジュ・ローダニアン」。 それ以外にも、「品種毎に収量が毎年異なるので、天候リスクを分散させ、味わいを補完し合える」というビジネス面での有難い側面もある。例えば、「クアチュオール」というキュヴェの白ワインは、セミヨン、ヴィオニエ、シャルドネ、ルーサンヌのブレンド。2023年は各品種ほぼ同等比率のブレンドだったが、2024年はシャルドネが80%以上を占めた。ブレンド比率は異なるが、「クアチュオール」という世界観はそのままに。生産者の意図を感じながら、毎年異なる味わいを楽しめるワインなのだ。 ▲ 「トロワジエーム」より。「クアチュオール」の美しい色調にうっとりする。 困難は一つずつクリアしていく...
長野・ヨネファーム東御
日本ワインコラム |ヨネファーム東御 インタビューのお相手、米倉さんとは、地元で大人気のやきそば・ワンタンのお店「開花亭」で待ち合わせ。到着時には既に長い行列だったが、食い意地の張った我々にとって行列なんて怖くない。米倉さんへのご挨拶も早々に、熱々の焼きそばとワンタンを汗タラタラで食すところからのスタートとなった。こんな素敵なお店での待ち合わせを提案して下さったくらいだし、さぞかし何度も来店しているかと思いきや、2回目という米倉さん。普段はきっと、畑仕事が忙しくて、のんびりランチとはいかないのだろう… ▲ くしゃっとした目元が印象的。優しい笑顔の米倉さん。 2018年に東御市でワイン用ブドウ栽培を開始した米倉さんは、3ヶ所に跨る約5haの畑で多種多様なブドウ品種を一人で栽培するスーパーマンだ。口数は少なめ。反射神経的に言葉を発するのではなく、自分の中で納得したことだけを話すからだろう。だからこそ、発せられる言葉には強い意志を感じる。そんな米倉さんの現在とこれからについて色々とお話を伺った。 広がる畑の管理 米倉さんがワイン業界に足を踏み入れたのは50歳を目前にした頃。その前から15年間毎月ワイン会を開催し、友人達と世界各地のワインを楽しんだり、ブルゴーニュ、ローヌ、カリフォルニアといった銘醸地を訪問し、栽培・醸造を体験したりと、趣味以上仕事未満の熱量でワインと関わってきたが、とうとう仕事にする決意を固め、25年勤務した通信系会社を退職。2015年に東京、神楽坂でワインバー&ショップをオープンしたが、ワインとの関係が深まる中でワイン造りへの興味が増し、開店数年で再度転身を図る。長野県東御市が募集していた千曲川ワインアカデミーの3期生として、2017年に移住するのだ。そして、信州うえだファームの研修生として農業研修も受け、2019年に独立する。 ▲ ヨネファーム東御のインスタより。千曲川ワインアカデミーの同期との一枚。いい関係性なのが見て取れる素敵な一枚だ。 米倉さんのブドウ畑は、長野県東御市の3つの場所(鞍掛金井、祢津御堂、海善寺)に跨る。東御市は降水量が少なく、冷涼ながら日照時間は長い。また、畑は540mから780mと標高が高い場所にあり、昼夜の寒暖差のあるワイン用ブドウ栽培に恵まれた場所だ。 独立後すぐに植栽開始したのは鞍掛金井。0.5haの広さに白赤6種類のブドウが植わっている。その後、巨峰が植わる海善寺の畑の管理も開始し、2019年には、東御市がワイン用ブドウ団地として立ち上げた祢津御堂での植栽を開始する。広さ4.1haの畑で、赤白11種類のブドウを栽培している。これだけではない。畑に足を運ぶことが難しくなった千曲川ワインアカデミー同期の0.7haの畑の管理もお手伝いしているというのだから、どこにそんな体力があるのか…⁉と目が点になる。 持続可能なブドウ栽培を目指して 「できるだけ薬は使いたくはないけど、ブドウができないと話にならない」、と米倉さんは語る。東御市はワイン用ブドウ栽培に適した場所ではあるが、「日本の中で」という前提が付く。高温多湿な日本は、世界の銘醸地と比べてブドウが病気にかかるリスクは格段に高い。ブドウ栽培を始めてから3年目までは年3回程度の農薬散布で問題なかったが、4年目になると一気に病気が蔓延して大変な事態に陥ったそうだ。リュー・ド・ヴァンの小山さんも同じことを語っていたが、若木は菌やウイルスの蓄積がなく、無農薬でも大きな問題にはならないことが多いが、年数を重ねるにつれ、病原物質が蓄積され病気が発生しやすくなるのだ。 こういった経験も踏まえ、ビジネスと環境の両立の観点から減農薬栽培を主軸に据え、農薬散布量はJAの防除暦で推奨される量の半分程度に抑えているそうだ。 ▲ 祢津御堂にある米倉さんの畑の様子。眼下に市街地が見え、遠くには八ヶ岳、霧ヶ峰、北アルプスといった美しい山々の絶景が!また、畑の前にはビジターセンターである「ワインテラス御堂」があり、ワインの試飲・販売スペースもある。 気候変動の影響だろうか、極端な空模様になることが増えた昨今。これまでとは異なる対策が求められつつある。2024年は猛暑に加え、8月後半から9月にかけて雨が断続的に降り続く難しい年で、収穫前に一気に晩腐病というカビの病気が広がったそうだ。特に黒ブドウへの影響が大きく、収量は予定の半分程度、メルロに至っては9割方がダメになってしまった。今後も異常気象が続くと言われており、農家にとっては困難な時代だ。米倉さんの畑では雨除けは特に必要としてこなかったが、今年からは祢津御堂のメルロについては、フルーツゾーンだけの雨除けを始める予定だそう。薬に頼らない対策を色々と考えておられるのだ。 ▲ 祢津御堂の畑は、緩やかな斜面だ。広いスペースなので草刈りだけでも本当に大変… 一つに絞るのはもったいない 3つの畑では、白ブドウ6品種(シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン、リースリング、セミヨン、ルーサンヌ、ヴィオニエ)、黒ブドウ9種類(シラー、ムールヴェルドル、グルナッシュ、メルロ、カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨン、プティ・ヴェルド、ピノ・ノワール、巨峰)と、多種多様なブドウを育てている。これらはフランスの主なワイン品種であると同時に、世界的にも認知度が高い。 「品種それぞれに美味しさがある。1つに絞るのはもったいないし、決められない」、と米倉さんは言う。ワインに対する深い愛情を感じる言葉だ。これまでは、各品種の収量が少ないということもありブレンドすることが多かったが、いざブレンドしてみると、ブレンドしたからこそ得られる美味しさや組み合わせによる新たな発見もあり、手応えを感じている。 例えば、「メランジュ・ボルドレーズ」というキュヴェでは、ボルドー・ブレンドとして、メルロ、カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨン、プティ・ヴェルドといった品種がブレンドされているし、「メランジュ・ローダニアン」は、ローヌ地方のワインを彷彿とさせる、シラーとムールヴェルドルのブレンドに仕上がっている。品種や比率は毎年変わるが、こういった楽しさが提供できるのは、多品種を育てているからこそ。 ▲ 千曲川ワインアカデミーの同期と立ち上げたブランド「トロワジエーム」の名を冠したオンラインストア、「トロワジエーム・ワインズ」より。左が「メランジュ・ボルドレーズ」、右が「メランジュ・ローダニアン」。 それ以外にも、「品種毎に収量が毎年異なるので、天候リスクを分散させ、味わいを補完し合える」というビジネス面での有難い側面もある。例えば、「クアチュオール」というキュヴェの白ワインは、セミヨン、ヴィオニエ、シャルドネ、ルーサンヌのブレンド。2023年は各品種ほぼ同等比率のブレンドだったが、2024年はシャルドネが80%以上を占めた。ブレンド比率は異なるが、「クアチュオール」という世界観はそのままに。生産者の意図を感じながら、毎年異なる味わいを楽しめるワインなのだ。 ▲ 「トロワジエーム」より。「クアチュオール」の美しい色調にうっとりする。 困難は一つずつクリアしていく...

長野県・アクアテラソル馨光庵
日本ワインコラム |アクアテラソル馨光庵(けいこうあん) なにせ絶妙なのだ。 独立独歩のようで繋がっている。信頼と尊敬の隣に緊張感がある。 2023年9月、東御市鞍掛にオープンしたワイナリー、アクアテラソル馨光庵を舞台にした主人公たちの関係だ。代表を務める平井さんと醸造責任者の中田さんの話を聞くと、いい意味で「人生何が起こるか本当に分からないなぁ」という気になる。 ▲ ワイナリー外観。下見板張の外壁と瓦葺き屋根が美しい伝統的な日本家屋の建物だ。 ▲ 左側が平井さん、右側が中田さん。 始まりの前夜 ビジネスパートナーであり、師弟関係でもある平井さんと中田さん。ワイナリーを建てる前までは全く別の人生を歩んでいた。 平井さんの歩み ▲ チャーミングな笑顔で周りを虜にする平井さん。 平井さんは東京の司法書士事務所を経営するビジネスマンであり、ワインラバーでもあった。ワインへの気持ちが高まり、2018年に事務所を後進にゆずり、52歳で長野県に移住。千曲川ワインアカデミーでワイン造りを学び、信州うえだファームで農業研修を受け、就農する。東京での安定した生活を捨てられたのは、ワイン愛の強さ故かもしれないが、好奇心の強さ、柔軟な考え方、思い切りの良さといったところにも秘密がありそうだ。また、人との出会いを縁に変えるチャーミングな人柄を忘れてはいけない。 農業研修先でのカーヴ・ハタノの波田野氏との出会いが転機となる。「波田野さんの造るワインが本当に美味しくて、衝撃が走った!ワイン造りの師匠ではあるが、自分は波田野さんの大ファンで追っかけ。家のセラーは波田野さんのワインだらけで、垂直で全て揃えている」、と豪語するほど。好きになったら一直線。ツンデレなんて言葉は辞書にないほど、好き光線が出る。この光線を浴びた人は、平井さんを好きにならずにはいられないのだ。 中田さんの歩み ▲ 中田さんの語り口は揺るぎなく、説得力に満ちている。 一方の中田さんも東京出身。祖父の代まで農家を営む家で生まれた。農家になりたいという夢を追いかけ、2012年、ヴィラデスト・ワイナリーへの就職を機に長野県東御市に移住。ワイナリースタッフも、併設のレストランで提供する野菜栽培を担っていたそうだ。そして、当時ヴィラデストで栽培・醸造の責任者を務めていたのが波田野さんだった。「波田野さんも自分も移住組。若造の頃から公私共に本当にお世話になって、心から信頼している先輩」だと言う。 波田野さんが独立後、中田さんがヴィラデストで栽培・醸造の責任者を務めたが、2019年に独立する----野菜農家として。えぇっっ‼ワイナリーじゃないの~!?と思ってしまうが、元々野菜農家になりたかった本人にとっては当然の選択だ。中田さんにとって、玉ねぎもブドウも同じ農作物。ただ、独立後もシャルドネの一枚畑は持ち続け、カーヴ・ハタノで委託醸造していたという。 「ワイン」ではなく、「農業」からスタートしているからこその選択だ。周りと比較せず、夢を持ち続け、臨機応変に動く。どっしりしつつ軽やかなのだ。 それぞれの歩みが重なる~ワイナリーの始動 別々の道を歩んでいた2人を結びつけたのは、波田野さん。ある日、野菜農家として汗を流していた中田さんに天の一言が下り、平井さんと中田さんが急接近するのだ。 (波田野)「ちょっと遊びの話なんだけど、とある人ともう一軒ワイナリーを建てようと思っててさ。お前、醸造長やるだろ?」 (中田)「え?あ…はい!」 これで決まったらしい。「とある人」とはもちろん平井さんのこと。平井さんの熱意をくんだ波田野さんが一役を買ってくれたのだ。「手にしたものは地域のために活かしなさい」と波田野さんから常々言われていたそうだが、野菜農家として独立したはずの中田さんが即決するとは…恐るべし師弟関係! ▲ アクアテラソル馨光庵HPより。平井さんと中田さんを結びつけた波田野さんにも色々とお話を伺ってみたい。 思いが詰まったワイナリー建設...
長野県・アクアテラソル馨光庵
日本ワインコラム |アクアテラソル馨光庵(けいこうあん) なにせ絶妙なのだ。 独立独歩のようで繋がっている。信頼と尊敬の隣に緊張感がある。 2023年9月、東御市鞍掛にオープンしたワイナリー、アクアテラソル馨光庵を舞台にした主人公たちの関係だ。代表を務める平井さんと醸造責任者の中田さんの話を聞くと、いい意味で「人生何が起こるか本当に分からないなぁ」という気になる。 ▲ ワイナリー外観。下見板張の外壁と瓦葺き屋根が美しい伝統的な日本家屋の建物だ。 ▲ 左側が平井さん、右側が中田さん。 始まりの前夜 ビジネスパートナーであり、師弟関係でもある平井さんと中田さん。ワイナリーを建てる前までは全く別の人生を歩んでいた。 平井さんの歩み ▲ チャーミングな笑顔で周りを虜にする平井さん。 平井さんは東京の司法書士事務所を経営するビジネスマンであり、ワインラバーでもあった。ワインへの気持ちが高まり、2018年に事務所を後進にゆずり、52歳で長野県に移住。千曲川ワインアカデミーでワイン造りを学び、信州うえだファームで農業研修を受け、就農する。東京での安定した生活を捨てられたのは、ワイン愛の強さ故かもしれないが、好奇心の強さ、柔軟な考え方、思い切りの良さといったところにも秘密がありそうだ。また、人との出会いを縁に変えるチャーミングな人柄を忘れてはいけない。 農業研修先でのカーヴ・ハタノの波田野氏との出会いが転機となる。「波田野さんの造るワインが本当に美味しくて、衝撃が走った!ワイン造りの師匠ではあるが、自分は波田野さんの大ファンで追っかけ。家のセラーは波田野さんのワインだらけで、垂直で全て揃えている」、と豪語するほど。好きになったら一直線。ツンデレなんて言葉は辞書にないほど、好き光線が出る。この光線を浴びた人は、平井さんを好きにならずにはいられないのだ。 中田さんの歩み ▲ 中田さんの語り口は揺るぎなく、説得力に満ちている。 一方の中田さんも東京出身。祖父の代まで農家を営む家で生まれた。農家になりたいという夢を追いかけ、2012年、ヴィラデスト・ワイナリーへの就職を機に長野県東御市に移住。ワイナリースタッフも、併設のレストランで提供する野菜栽培を担っていたそうだ。そして、当時ヴィラデストで栽培・醸造の責任者を務めていたのが波田野さんだった。「波田野さんも自分も移住組。若造の頃から公私共に本当にお世話になって、心から信頼している先輩」だと言う。 波田野さんが独立後、中田さんがヴィラデストで栽培・醸造の責任者を務めたが、2019年に独立する----野菜農家として。えぇっっ‼ワイナリーじゃないの~!?と思ってしまうが、元々野菜農家になりたかった本人にとっては当然の選択だ。中田さんにとって、玉ねぎもブドウも同じ農作物。ただ、独立後もシャルドネの一枚畑は持ち続け、カーヴ・ハタノで委託醸造していたという。 「ワイン」ではなく、「農業」からスタートしているからこその選択だ。周りと比較せず、夢を持ち続け、臨機応変に動く。どっしりしつつ軽やかなのだ。 それぞれの歩みが重なる~ワイナリーの始動 別々の道を歩んでいた2人を結びつけたのは、波田野さん。ある日、野菜農家として汗を流していた中田さんに天の一言が下り、平井さんと中田さんが急接近するのだ。 (波田野)「ちょっと遊びの話なんだけど、とある人ともう一軒ワイナリーを建てようと思っててさ。お前、醸造長やるだろ?」 (中田)「え?あ…はい!」 これで決まったらしい。「とある人」とはもちろん平井さんのこと。平井さんの熱意をくんだ波田野さんが一役を買ってくれたのだ。「手にしたものは地域のために活かしなさい」と波田野さんから常々言われていたそうだが、野菜農家として独立したはずの中田さんが即決するとは…恐るべし師弟関係! ▲ アクアテラソル馨光庵HPより。平井さんと中田さんを結びつけた波田野さんにも色々とお話を伺ってみたい。 思いが詰まったワイナリー建設...